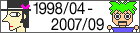|
|
||
PR
      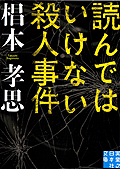 archive |
[今日の独言(ひとこと)] 【ふたたび能登半島へ】
2019年のゴールデンウィークに、能登半島を一周する旅行に出かけた。
奈良から京奈和自動車道に乗り、京滋バイパスから名神高速を通って北陸自動車道に入る。 金沢から、のと里山海道に入って、海沿いのルートをぐるりと回った。 千里浜の浜辺を車で走り、近くにある水圧の弱い洗車場で車を洗い、宇宙科学博物館で思いの外レアな展示物に驚いて謎の宇宙人マスコットキャラクターにも会った。 志賀原発の脇を通り抜けて、世界一長いベンチという微妙な観光名所も立ち寄り、輪島市の港近くのパーキングに車を停めて車中泊をした。 車中泊はエンジンを切ると夏は暑くて冬は寒いので、春秋の時期が最高だ。 他にも多くの車が停まっていたのを覚えている。 翌日は早朝から輪島の朝市に寄って食べたり買ったりしてから出発。 昨日と同じく海岸線を走って千枚田という海に面した棚田を見たが天気は悪かった。 塩の駅という塩が名物の観光地も訪れて、半島の先にある「狼煙」といういかにもな道の駅で降りて禄剛崎灯台へ行くと、まさしく能登半島の先っぽに辿り着いた。 その後は南下して珠洲市にあるランプの宿を見下ろしつつひたすら走る。 「道の駅すずなり」は名前が可愛いので立ち寄り、能登島へも立ち寄りたかったが時間がなかったので七尾市の和倉温泉で一泊した。 翌日には氷見市で藤子不二雄(A)のアナーキーな息吹を感じ、滑川にはホタルイカのミュージアムがあるというので行かねばならず、その後は高速道路を爆走して奈良へと帰った。 車中泊を兼ねての旅行だったが、割と無茶なスケジュールだったと思う。 結局、何時間車を運転していたのか、きっとかなり疲れただろう。 でも、今はそんなネガティブな記憶は全く残っていない。 いくら思い返しても、ただ、めちゃくちゃ楽しかった、行って良かったという思い出しかないのだ。 天災は避けられないもの、仕方のないものと理解していても、やはり理不尽で、無慈悲で、やるせない。 なぜ、あんな素敵な地域が、こんな被害を受けなければならないのか。 恐らく、たった数時間前、あるいは直前にも、現地で初詣に訪れた人々が今年の安全と平穏を祈願していたことだろう。 その思いを一瞬で反故にされた人々の絶望感を思うと、怒りとも悲しみとも付かない気持ちにさせられた。 元日の大地震は図らずしも神様の不在を証明することになったと私は思う。 あるいは、たとえ神様がいたとしても、地震から守ってはくれないということなのかもしれない。 結局、人が守り、人が助け、人がなんとかするしかない。 もう一度、あの素敵な景色の中で旅ができるよう、私も願うことなく、祈ることなく、協力したい。 [一日三報] [Gigazine] キヤノン・ニコン・ソニーが写真にデジタル署名を埋め込むカメラ技術を開発中、AIが生成した精巧な偽物と写真を区別するのに役立つ可能性あり
急造するフェイク画像への措置としてメーカーも苦心しているらしい。 とはいえカメラ機能だけで対抗しようにも難しく、フェイク画像を見極めるのではなく、これはフェイク画像ではないと証明するくらいのことしかできないだろう。 最終的には、AIが作るフェイク画像を、AIが見破る社会になると思う。 [Forbes] なぜ今でも多くの人が占星術を「信じる」のか、心理学な理由
星占いも風水も四柱推命も、気分転換のために使われる偽薬的サービスだ。 ただ、大多数の人はそう思って利用しているが、まれに心の底から信じ切っている人もいるから気をつけなければならない。 [共同通信] 「走って逃げるカタツムリ」 高校生ら学術誌に発表
今日の無駄な抵抗。 ミジンコも危機を感じるとゆっくりとツノを伸ばすと聞いたことがある。 とはいえ人間もライオンに囲まれたら心拍数を高めて逃げようとするだろうし、風邪をひけば体温を上げて咳を出して抵抗し、結局自身がダメージを受けている。 無駄であっても抵抗するのが動物の本能で、それがなければ繁栄もない。 ラオウも無抵抗な奴をシバいていた。 [今日の独言(ひとこと)] 【心の平和に散歩のススメ】
京都の銀閣寺と南禅寺を結ぶ約2kmにわたる散歩道は『哲学の道』と呼ばれている。
琵琶湖からの疎水に沿った風情ある道で、春には桜の名所としても知られている。 『善の研究』で知られる哲学者の西田幾多郎が毎朝この道を歩いて思想に耽っていたことにちなんで名付けられたという。 なお、氏の名前を私はずっと『にしだ いくたろう』と思い込んでいたが、本当は『にしだ きたろう』と読むそうだ。 ゲゲゲの謎とは関係ない。 ミステリ好きなら島田荘司の『占星術殺人事件』に登場した舞台として知っている方もいるだろう。 名探偵・御手洗潔がわちゃわちゃと走り回っていた道だ。 私も四半世紀前に言ったり来たりした覚えがある。 作品で同じく道沿いの店として登場した喫茶「若王子」も訪れたが、今はもう閉店しているそうだ。 私は哲学者でも名探偵でもないが、毎日夕方には近所を散歩に出かけている。 なんだかお爺さんみたいな話だが、これには理由がある。 同じように十数年にわたりジョギングをしていたのだが、数年前に膝を壊してしまったので、仕方なく散歩に置き換わったのだ。 ゆえに私の散歩は若者のぶらぶら歩きとは全く違う。 まるで売り切れ必至の限定グッズをゲットするために駅から射出されたマニアにも匹敵するスピードでスタコラしている。 だから、どうか道幅一杯に広がって喋り歩かないでほしい。 私がジョギングや散歩を続けるようになったのは思想に耽るのではなく、運動不足の解消が目的だった。 しかしこの頃は、なかなか頭の健康にも良いように感じてきた。 ひとつにテンポよく呼吸を繰り返しながら足を動かし続けていると、頭の中がすっきりする。 正確には歩く以外の何もできないので、何も考えられなくなるのだが、それが禅や修行に似た無の境地を得ているような気がするのだ。 家でじっとしていても、すぐにスマホをいじったり、本を読んだり、ゲームをしたり、掃除をしたりしてしまう。 それが何もできず、ただ歩くしかないとなると、脳が暇になって休まるような感覚が得られるのだ。 同じく、怒りや悲しみや不安といったネガティブな感情も遠ざけられて気を鎮めることができる。 今の自分には歩き続けることしかできないのだから、あれこれ悩み考えても仕方ないと思えるようになり、そのブランクが気持ちやタスクの整理に繋がるようだ。 ということで、近頃気落ちしてどうにもならない人には散歩をお薦めしたい。 そんな時間も暇もない人ほど、無理矢理出かけた方が良い。 その間に事態も気持ちも好転することもあるだろう。 まあ、その代わり、雨だのなんだので散歩に出られない日のストレスは半端ないが。 [一日三報] [CNN] 初代版ミッキーマウスの著作権が失効、パブリックドメインに
あの手この手で無理矢理に引き伸ばしてきた著作権もついに失効するらしい。 ただし初代版とか、微妙な線引きをしているようだ。 それは初代版は今のミッキーマウスとは別物だと自ら否定しているようなものだと思うが。 というわけで、今後は昔のインターネットのようにキッズたちが笑いそうな露悪な(初代)ミッキーマウスが出てくると思う。 というか、できる奴らはすでに完成させて公開の日を待っていることだろう。 [産経新聞] PCキーボードに対話型AIキー 米MS、新機種で導入
今日のデファクト・スタンダード ってこの頃は言わなくなったよね。 恐らく凄い機能だと思うし、きっと世の中が便利になると思うが、標準搭載で削除不可能にするのはどうか止めてください。 邪魔なんだよ、色々と。 [AFP] 暦が一致 1996年のカレンダーを再利用
へえ、そうなんだと思ったけど、古いカレンダーを引っ張り出してくるほど、カレンダーに困ることってないよね。 [今日の独言(ひとこと)] 【十二支に龍が選ばれた理由】
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。 2024年、令和6年、今年は辰年とか。 私は毎年の初詣は、その年の干支にちなんだ寺社仏閣へ訪れている。 辰年の龍にまつわる寺社仏閣は非常に多い。 来年の巳年、蛇にまつわるところも多い。 再来年の午年、馬も神馬として祀られているところはある。 問題は3年後の未年、羊がなかなか難しい。 元々日本には存在しなかった動物なので、祀りにくかったのだろう。 一応、愛知県に羊神社(ひつじじんじゃ)はあるが。 十二支の中で存在しなかった動物といえば、辰年の龍こそまさしくそうだ。 しかしその格好良さから大いに崇められて、唯一無二の地位を獲得した。 格好良さとは強さと美しさであり、人知を超えた憧れでもある。 ゆえに龍は神仏がごとき力と立場を手に入することができたのだろう。 しかし、どうして十二支に龍が含まれることになったのか。 無邪気な人なら、動物同士の追いかけっこの逸話を持ち出すかもしれない。 物知りさんなら、古代中国の文人・王充が暦の読み方を民衆に広めるために生み出したと説明するかもしれない。 ただ、それが事実であったとしても、龍を持ち出す必要はなかった。 別の動物でも、音が似ていればそれで良かったはずだ。 私が考えるに、たぶん、龍が格好良かったからだ。 「僕たちが考えた格好良い動物」だったから、みんなに紹介したかったのだ。 もしも龍がいなければ、十二支など畜生どもの集まりに過ぎなかった。 今年はネズミです、ウシです、サルです、イヌですと言われても、誰も興味を持たなかっただろう。 しかし、その中に格好良くて神秘的な龍を含めたことで、民衆は興味を持ち、残り全ての動物にまで神性があるように感じて、ありがたがるようになった。 龍が民衆の想像力を刺激して、おのずと十二支のステージを高め、ポケモンなど遠く及ばないキャラクタービジネスを確立させたのだ。 ということで、格好良さは正義であり、世界を変える力がある。 今年はそれを意識しつつ過ごしていきたいと願っている。 具体的には、まあ、おいおいぼちぼち考えていこうか。 [一日三報] [読売新聞] 寄生虫「アニサキス」1億ワットで感電死…熊本大学、4年費やしアジで技術確立
むしろ9999万ワットでも感電死しないアニサキスは凄いのではと思ったが、そういう話ではないみたい。 それでも死骸から引き起こされるアレルギーは残りそうで、やっぱり怖い。 [東京新聞] ポイ活過熱の余波?スマホ振り子で不正に歩数カウントか…1カ月に200万歩以上も 川崎市のウオーキングアプリ
特に意識はしていないが、私のスマホにもウォーキングアプリは入っている。 なんか勝手にポイントが付くので、まあお得といえばお得なのだろう。 しかしここまでの情熱はないわけで。 というかランキングを無くせば良いだけの気もするが。 [CNN] ファストフード店で就労2カ月の判決、店員に皿投げた客に 米
今日のカスハラ。 日本ではこういう懲罰はないが、これはこれでアリの気もしたり。 もう少し店員さんを守れるシステムがあったほうが、きっと店側も客側も助かる世の中になると思う。 |
|
| |
||