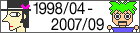|
|
||
| archive
|
[今日の独言(ひとこと)]
関西電力の子会社が、不在時に荷物を受け取れる宅配ボックスを電柱の隣に設置するサービスを始めたらしい。
宅配ボックスは休日でも夜間でも荷物の受け取りができる上、新型コロナウィルスの感染予防で直接荷物を受け取りたくない場合にも利用できるとして、配送業者も受け取る側にも有益なサービスだ。 関西電力の管轄内には約270万本の電柱があるというので、これからサービスが拡大できるかどうか実証実験を行うそうだ。 町中のボックスといえば思い出されるのが電話ボックス。 あれなども宅配ボックスに利用する手もあるように思ったが、今はもうあまり見かけなくなってしまった。 統計によると、現在国内にある公衆電話の数は15.1万台で、2000年の73.5万台と比較すると20年で1/5近くも激減してしまった。 なお、この数は電話ボックスタイプ以外の公衆電話も含まれるので、町中に設置されていた箱形タイプの物はさらに少ない可能性があるだろう。 理由はもちろん携帯電話・スマートフォンの普及だ。 わざわざ10円玉を握り締めて、あの癖のあるドアを開ける必要もなくなった。 そのため近頃は小学校などでもNTTから講師を招いて、子供たちに公衆電話の使い方を指導することもあるらしい。 災害時など緊急事態で利用することもあるからだ。 ちなみに使い方は、まず横に付いている受話器を持ち上げて、という説明から始まる。 家に固定電話のない家も多いため、受話器という謎の通話機すら持ったことのない子が多いのだ。 電話ボックスがなくなっているのは外国でも同様のことだが、イギリスのロンドンでは天板にソーラーパネルを設置して無料でモバイル機器の充電ボックスに利用する試みも行われているらしい。 ロンドンといえば赤色で丸い屋根が可愛い電話ボックスが街のシンボルにもなっているので、文化的存在価値として残しておきたい風潮もあるのだろう。 また上海では、第5世代移動通信システム(5G)の小型基地局に利用するサービスが始まっているらしい。 5Gは高速大容量通信が売りだが、実は通信可能エリアが3Gや4Gと比べて物凄く狭いので、新たに多数の基地局を設置する必要があるからだ。 最近は日本でも電話会社のCMでやたらと推しているが、郊外では使えないエリアがかなり多く発生するだろうから、まだあまり期待しないほうがいい。 家でガンガン使えると思ったら大間違いだ。(その際は4G/3Gに自動で切り替わる) 便利な通信設備から街の不要な箱物へと変わってしまった電話ボックス。 しかし、せっかく町中にあったのだから、今後何か有効利用する手立てはあったのではないだろうか。 宅配ボックスにとか、通信ボックスにとか、なんにせよ、そんなに急いで撤去しなくても良かったんじゃないだろうかと今は思っている。 [一日三報]
[CNN] ペットの鹿が散歩中の女性襲う、飼い主に出頭命令 米コロラド州
まったくこれだから奈良県民は、と思ったらコロラド州の話だった。 シカ、というかウシやヒツジも含めた偶蹄目は、管理しやすいかもしれないけど、やっぱりそこまで聞き分けが良くなることもないと思う。 奈良公園の鹿もフレンドリーに見せかけているけど、別にヒトが好きなのではなく、結局エサをねだるために近づいてくるものです。 まあ、おごってくれるなら嫌いな人が相手でも愛想くらい見せるわな。 [産経新聞] タランチュラ、家に戻る 茨城
「父、帰る」的な見出し。 自力で帰宅したなら見直したが、やっぱり連れて帰された模様。 ちなみにタランチュラは俗称で、正式名称はこの画像のものはオオツチグモかと。 大土蜘蛛、と書くと体長3メートルくらいに思えるのでやっぱり怖い虫です。 涅槃で待つ。 [AFP] 「不毛の砂漠」に樹木18億本、衛星画像とディープラーニングで発見 アフリカ
今まで知られていなかったというのが興味深い。 手の平で世界地図が持ち歩けて、何億光年も離れたブラックホールも撮影できるというのに、サハラ砂漠に木が生えているのは知らなかったという。 たぶん先入観が邪魔をして見えなくなっていたのだろう。 知ったところでどうする、という話もあるわけで。 人生においてそういうシーンは結構あるかもしれない。 [今日の独言(ひとこと)]
先日、とある地方新聞社のサイトでで気になる記事を見つけた。
内容を書くとどこの新聞記事かは丸分かりになってしまうが、そこは分からない振りをしておいていただきたい。 その記事の見出しには『女子中学生2人に熊谷署が感謝状』とあった。 内容は今月中頃、中学生2人が下校途中、水路に落ちて助けを求めていた70代の男性を発見。 近くの大人たちを呼んで引き上げて命を救ったとして、後日管轄の警察署から感謝状が贈られたということだ。 いちゃもんの付けようもない素晴らしいニュースだった。 ところが記事に掲載されている写真を見て不思議に思った。 そこには応接室で警察署員らしき人物と対面する二人の中学生が映っていたのだが、一人はスカートの制服を着て、もう一人は黒い詰め襟の学生服を着ていたからだ。 記事の見出しには『女子中学生2人』とあったが、一方は明らかに男子中学生の制服を身に着けている。 ということは、見出しが間違っていたのか、いや、そこで判断に迷ってしまった。 もしかして、この子は『男子の制服を着ている女子』なのではないだろうか? 詰め襟の中学生は短髪で品行方正な雰囲気があり、まだ顔に男らしい精悍さ(これも判断は難しいが)は見られない。 しかもコロナ禍の時勢なので、写真に映る三名は共に大きな白いマスクで顔半分を覆っており男女の判別が付きにくかった。 それでは名前を見れば分かるだろうと思ったが、当の中学生は「○○聖」さんという方らしい。 これも「さとし」や「きよし」と読めれば「せい」や「きよ」と読むこともあり、昨今の自由な命名からでは判別が付かなかった。 私は別に女子が男子の制服を着ていても、「聖」と書いて「せいんと」や「きらりん☆」と読んでも全く気にしない。 彼あるいは彼女がどういう精神・主義・身体特徴であったとしても、二人のお手柄には全く変わりないと思っている。 むしろ興味を惹かれたのは、この内容を見ても見出しの間違いと即断せずに、待てよと思ってしまう自分の心境の変化だった。 LGBTやジェンダーの話には積極的に関わっていないが、それでもこんな風に感じてしまう世の中、自身になっているのだなと思った次第だ。 それはともかく、一応ミステリ作家なので、疑問を放ってはおけない性がある。 ここでうやむやにしては気になって眠れなくなってしまうので、手間を掛けると思いながらも新聞社に問い合わせてしまった。 結果、『女子中学生2人』は『中学生2人』の間違いで、当の人物は男子中学生とのことだった。 指摘を感謝する丁寧なメールとともに記事の見出しも早々に修正された。 ああ、やっぱりそうなのかと思いつつ、別に放っておけば良かったと少し反省した。 でも、せっかくの良い記事なので、修正したほうがきっと関係者の方々も嬉しいだろうと思っておきたい。 そんな一件だった。 正しいことをしているならば、性別や服装なんて路上に捨てられたマスクよりどうでも良いことだ。 [一日三報]
[BBC] 南米ナスカの地上絵に巨大ネコ 2000年前に作成か
今日の考古学。 ナスカに描かれていなかったら間違いなく清掃員に消されるレベル。 有名なハチドリやクモのような幾何学的でも神秘性もないが、ようやく人間らしさが感じられる作品だと思う。 最初にこれが見つかっていたら宇宙人説も超古代科学文明説も生まれなかっただろう。 なに笑とんねん。 [CNN] コロナ禍で街が閑散、スパイ任務「困難に」 英情報機関長官
ジェームズ・ボンドは格好良くて男前だけど、あの派手さはスパイに絶対向かないよね。 コロナ禍でライフスタイルが変わった人も多いが、スパイやギャングなど闇の人たちへの影響も大きいんだろうなと。 あと感染防止を理由に、国家による国民監視も進んでいる気がしたり。 逆にデータによる信用さえ得られれば、誰にも怪しまれない人になれる気もしたり。 これからのスパイ物はそのあたりを扱ったストーリーになっていくかも。 [産経新聞] 閣僚の名刺や甲子園の土も出品、フリマサイトの薄い線引き
何を今さらといった印象。 20年前にヤフオクができた時からオークションとは名ばかりのネット闇市だったわけで。 メルカリはスマホひとつで簡単にできるようになったから、さらに玉石混淆というか、砂漠で砂金を探すような場所になっているかと。 しかし土や名刺まで売れるというなら、私も一丁、こしらえてみようかしらね。 [今日の独言(ひとこと)]
このメルマガを執筆しているのは10月9日の金曜日であり、今、西日本のここは昨日からの雨風が延々と続いている。
強い勢力の台風14号が、じわりじわりと近づきつつあるからだ。 このメールマガジンが配信される、10月12日の月曜日の夜には関東を抜けて太平洋側へと東進し、熱帯低気圧へと変わっているだろうか。 各地に大きな被害がなかった未来を今は祈っている。 台風というのは大人になると不安で煩わしい存在でしかないが、子供の頃はちょっと気分が高揚する気象イベントだったと記憶している。 激しい暴風雨によって日常が破壊されるドラマチックな展開は、映画やアニメに入り込んだような感覚を味わわせてくれるからだろう。 関係ないが『味わわせる』と『味あわせる』はどちらが正しいかというと、文法上では当然『味わわせる』が正解となる。 しかし文字にしても口に発しても『わ』の重なりが気になるらしく、半数くらいの人は『味あわせる』が正しいと思い込んでいるそうだ。 台風という呼び名の由来はちょっと変わっており、元々は「野分」(のわき・のわけ)と呼ばれており、他にも中国にならって「颶風」(ぐふう)と呼ぶなどもしていたらしい。 そのうち明治に入って欧州の影響が強くなると、彼の地で「タイフーン」と呼ばれていることを知って、そのまま「タイフーン」やそこから転化して「大風」(おおかぜ)と表すようになった。 そして明治の末には気象学者の岡田武松によって「颱風」(たいふう)という固有の名前が付けられた。 ところが面白いことに、英語の「タイフーン」の由来こそ台湾や中国福建省で激しい風のことを大風(タイフーン)と呼ばれていたことから名付けられたという。 つまり日本は巡り巡って「颱風」の呼び名を使うこととなり、結果日本語でも中国語でも英語でも同じような言葉が用いられるようになったそうだ。(諸説あり) なお「颱風」が常用漢字の「台風」に置き換えられたのは1956年(昭和31年)と、割と近代になってからのこと。 また「タイフーン」「ハリケーン」「サイクロン」は、それが現時点で存在している場所によって名称が変わる。そのため移動することによって呼び名が変わることもあるそうだ。 以上、台風に関する取り留めもない四方山話でした。 [一日三報]
[産経新聞] 無人機が次期戦闘機と編隊 防衛省が開発本格化
今日の戦争。 ガンダムのサイコミュはパイロットの脳波を感知して自走式のビーム砲台ビットを遠隔操作する仕組みだった。 優秀なパイロットが基地内の座席に並んで座り、遠隔操作で戦闘する時代になるわけで。 話だけなら格好いいけど、攻められるほうはやっぱり堪った物じゃない。 もうそこまでやるなら戦争もヴァーチャル・ゲームで勝敗を付けろよと。 [AFP] ウイスキーのたる熟成は無駄? 蒸留から出荷まで数日、米企業が新技術
ずっと以前から続いている研究。 根本あるのは風味も栄養も全部化学式で解き明かしたいという人類の欲求かもしれない。 これが広まると、評論家の文学的な風味の表現も興醒めな素材と化学式で語られるようになるのかも。 年代の古い貴重な酒というだけでバカ高い値が付いて、投機の対象にもなっている世の中もくだらないと思うけど。 [ITmedia] クボタ、NVIDIAと協業 「完全無人農機」実現に向け、エッジAI開発を加速
なぜ自動車業界のコンセプトモデルは大体悪そうな顔つきをしているのか。 そして実際に売り出されるようになると、若干丸く穏やかな表情になってしまうのか。 某ニュース記事で知られるようになった、謎の巨大企業NVIDIAも色々と手を出しているようで。 でも高齢化の激しい農業の自動化はかなり急を迫られていると思う。 誰が儲かるかは知らないけど。 [今日の独言(ひとこと)]
イギリスはウェールズの小さな村で、およそ一年半にわたって毎朝同じ時刻にインターネット接続が途切れるという謎の現象が発生していた。
運営会社の者が同地に赴いても、全く理由が分からず、ネットワークにも欠陥は見つからない。 機器やケーブルを交換しても現象は解消されなかった。 しかし、その後の詳しい調査により、家電製品から放出される電気的な干渉が原因であることを突き止め、それが一軒の家で使われていた古いテレビであることが判明した。 この家の住人が毎朝7時になるとテレビのスイッチを入れていたので、そのたびにインターネット接続が途切れていたということだった。 一方、ドイツのとある研究機関の発表によると、携帯電話が発する電磁放射線がミツバチやハエに負の影響を及ぼしている可能性があるらしい。 昆虫の体内でホルモンバランスが崩れて概日リズム(体内時計)や免疫系に障害が発生し、通常の活動が行えず個体数の激減に繋がっているとのことだった。 電波が人に悪影響を及ぼしていると言うとオカルトな話が出てくるが、実際無関係というのも楽観的過ぎるような気もしている。 声が聞こえるとか洗脳されるとかではなく、長期的に浴び続けているとミツバチのようにDNAの損傷やホルモンバランスに軽微な影響を及ぼしている可能性も否定はできないだろう。 ドイツのハインリヒ・ヘルツが電磁波を発見してから130年、現在のようなIT社会が訪れて20年。 私たちは人類がかつて体験したことがない電波の中で生まれ育って死んでいる。 数世代あとになってから、どうやらとんでもない健康被害が明らかになるのかもしれない。 とはいえ、完全電波なし生活に戻ることなど今さら不可能で、また自分だけ電波から逃れて仙人のような生活を送る気もない。 結局、半信半疑のまま電波の海を漂っていくしかないだろう。 どうせなら蚊やゴキブリを排除する電波が発見されればいいのに。 ミツバチへの影響が判明すれば、虫除けになる防虫Wi-Fiなどが登場するかもしれない。 [一日三報]
[CNN] 湖岸に漂着した「動物の脳」に仰天 米ウィスコンシン
今日のSF。 なかなか見慣れない漂着物。 SFだとこの脳を解析した結果、とてつもない知識や恐るべき予言を記憶していたことが発見されそうだが、現実ではそうはならない模様。 試しに何かの胴体に接続してみるとか、そういうこともできないのかな。 [産経新聞] 日本、月面に燃料工場 2030年代半ば実現目指す
今日のゲートウエー。 米国のアルテミス計画の一環かしら。 ワクワクさせてくれる話ではあるけど、日本が主導となると何となく上手くいかないというか、他国に掠め取られそうな気もしたり。 月旅行って現実味を帯びてくると、まあ別に行かなくてもいいかなって気になってくるのが不思議。 ハワイみたいなものか。 |
|
|
|
||