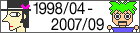|
|
|||||
| archive
|
 トナカイに憧れる鹿 [今日の独言(ひとこと)]
あっという間に、本当に、あっという間に年末が来たような気がする。
この一年は何だったのかと思っている人も多いだろう。 人間社会の脆さと汚さが白日の下にさらされた感がある。 美しさや温かさもあったが、それ以上の不安に連日苛まれた一年だった。 これは感染症への不安よりも、それによって右往左往する社会への不安のほうが大きかったように感じている。 私も新作小説が一本、流れ弾を受けたような形で出版できなかった。 飲食店や観光業なども死活問題どころか、もはや死に体状態にあるだろう。 IT関連企業や宅配サービス業は好調になったようだが、これも結局は社会活動の代替により盛り上がったものなので、全体が低迷してしまえば落ち込みは避けられない。 外に出なければマスクもいらないわけで、結局誰の得にもならない事態なのは間違いないだろう。 今年の春あたりに、もうこの一年は無かったことにしてはどうかと考えたことがある。 来年も2020年、令和2年、歳も取らずに進級もしない。 もちろん年度の税金も全額免除。 人生何十年と生きるのだから、一年くらい無視してもそんなに変わりはない。 人類が勝手に決めた区切りなんて宇宙に何の影響もない。 だから、みんな無かったことにして、もう一回2020年を始めたほうがいい。 そんな風に考えていた。 しかし、残念ながら、どうやら来年もまだこの騒動は続いてしまうらしい。 年が明けてもテレビやネットで、感染者数を速報しては無駄に煽られる日々が来るようだ。 最近は子猫の成長を伝え続けたほうが、視聴者の精神的にも有意義ではないかとも思い始めている。 というわけで、何かと残念な雰囲気の中ではあるが、今年の更新はこれにて終了。 一年間お付き合いいただき本当にありがとうございました。 また来年もよろしくお願いいたします。 小説ももう少し頑張って参ります。 [一日三報]
[読売新聞] ワクチン接種で「2か月飲酒控えて」、ロシア国民「それなら無理」と反発
今日のおそロシア。 政府は困るだろうけど、ロシア人はこうあって欲しいと思えるコメント。 国が変わると国民へのアプローチも変わるもので、いつも手元の原稿を淡々と読み上げるだけの日本の首相の姿勢を、真面目と見るか冷酷と見るか。 どこかの首相のように肩をいからせて、口角泡を飛ばして訴える姿勢を、熱血と滑稽と見るか。 どっちが正しいかは知らないけど、まあ、ズレたら嫌われるのは確かです。 [CNN] 運動アプリで歩く距離が1日1.6キロ伸びる 米などの研究
今日のスマホ奴隷たち。 でもわざわざお金を払ってまで不摂生と運動不足を叱られに行くフィットネスジムも流行っているわけで、こういうのも有効なんだろうなと思ったり。 多くの人は、何かをするよりも、させられるほうにリラックスを得る。 頭を使うのって面倒だからね。 [西日本新聞] ラーメン“発祥の地”は博多? 「水戸黄門が初めて」通説覆るか
記録によると水戸黄門こと水戸藩主・徳川光圀は、1697年6月16日に自分でラーメンを作って家臣に振る舞ったとか。 それが真実か嘘かは分からないが、まあ割と扱いに困る藩主だったのは確かなようだ。 なおリアル水戸黄門は別に諸国を漫遊して悪代官を退治したり印籠を見せびらかしたりもしていない。 でも全397巻226冊の歴史書『大日本史』の編纂に取りかかって藩の財政を傾かせたというから、やっぱり道楽な人で家臣は大変だったと思う。  鹿と紅葉 [今日の独言(ひとこと)]
戦国時代、織田信長の家臣として活躍した丹羽長秀。
その晩年は寄生虫による腹痛に苦しめられて、ついには「何ぞ腹の虫ごときに殺されようか」と自ら割腹して果てたという。 なおその時取り出された虫は、石亀に似て鳥のような嘴をもった「陽の亀積」(ようのかめしゃく)と呼ばれる怪物だったとか。 ふいに予想以上の寒波に襲われた先週、油断していたつもりはないが、ギックリ腰に襲われてしまった。 昼間にちょっと前に屈んだ瞬間に「あ、来た」と。 驚きよりも穏やかな気持ちで受ける死刑宣告。 腰が攣ったとでも言うのだろうか、一瞬痛みが走ってからはもう前にも後にも動けなくなった。 それからはもう、捻ると痛い、座ると痛い、動くと痛い、寝ても痛い。 患部を庇うために他の部位が緊張するので、結局全身が激しい筋肉痛に襲われるという有様だった。 ギックリ腰はドイツでは「へクセンシュス」と呼ばれ、直訳すると「魔女の一撃」となる。 英語でもそのまま「ウィッチズショット」と呼ばれており、つまり無属性衝撃魔法を腰に食らったようなダメージなのだ。 その原因も症状も正確には判明しておらず、病院でCTスキャンを受けても何も異常が見られないことが多い。(ヘルニアなら判明する場合もある) コキッといったなら、コキッと戻れば良いのに、そうもいかないようだ。 ただ原因については、経験だけで言うと長時間のデスクワークと冬の寒さが関係している気がする。 だからと言ってどうしようもないので、これはもうご愁傷様と思うしかないだろう。 腰という字は肉月(にくづき)に要(かなめ)と書くように、全身の要である。 腰痛はあらゆる動作に絡んで来る本当に厄介な代物だ。 丹羽長秀のように、何ぞ腰の痛みごときに殺されようかと、自ら刃を突き立てたい気持ちにもなる。 でも多分意味がないのでやらないほうが正解だ。 見た目には分からないが本人は必死なので、周囲の人は優しく接してあげて欲しい。 なお私の腰痛は次第に緩和しているらしい。 直ったら防御魔法を習得したいと思っている。 [一日三報]
[CNN] 犬は飼い主の言葉をどの程度理解している? 脳の測定で検証
知ってた速報。 でも犬と言っても犬種によって様々にも思う。 大きな犬は脳も大きいので、小さな犬よりも賢いような気もするが、さて。 そして言葉以外の信頼関係も確かにあると思う。 3つくらい覚えてくれたら充分よね。  たからさがしの秋 [今日の独言(ひとこと)]
太古の昔、荒野で暮らすサルの集団は厳しい環境の中で生き抜いていた。
猛獣のヒョウに襲われ、貴重な水場は別のサルの集団に奪われ、夜は大地に横たわって眠るしかなかった。 そんなある時、突如彼らの目の前に、屹立する巨大な黒いプレートが現れた。 およそ自然の物とは思えないそれを彼らは取り囲み、興奮し、やがてその表面に触れた。 その後、彼らは朽ちた動物の骨を拾うと、それを道具として扱い、武器として使うことを発見する。 これこそ知恵の萌芽、人類の目覚めであった。 そして高々と放り投げた一本の大腿骨は、膨大な時を経て、やがて宇宙船へと変貌した。 言わずと知れた『2001年宇宙の旅』の冒頭シーン、アーサー・C・クラークとスタンリー・キューブリックが1968年に作った傑作SF映画だ。 本当に面白いので知らない方には視聴をお薦めしたい。 眠くなるとか言う人は帰れと言いたい。 『3001年終局への旅』まで続く原作シリーズもお薦めしたい。 眠くなるとか言う人は帰れと言いたい。 ここで登場する謎の黒いプレートは『モノリス』と呼ばれており、異星人が地球のサルに人類への進化をうながした装置として、そのビジュアルとともに強烈なインパクトを残している。 本来『モノリス』とは自然に存在する『一枚岩』という意味で、オーストラリアのウルル(エアーズ・ロック)や日本にある『古座川の一枚岩』のことを意味している。 しかし映画の影響で『モノリス』といえばこの黒いプレートを想像する人が多いようだ。 東京の新宿モノリスビルもきっとそうだろう。 映画『インターステラー』のお助けロボも間違いなく意識しているはずだ。 さて映画の公開から52年、『2001年』から20年経った現在。 なぜか先月あたりから、そんなモノリスが世界中で目撃されるニュースが続いている。 11月18日にアメリカ・ユタ州の砂漠に存在することが発見されて以来、ルーマニア、カリフォルニア州、ネバダ州、オランダ、イギリス、コロラド州、コロンビアと相次いで見つかった。 いずれも鏡のように滑らかな金属の一枚プレートで、それ以外には何の特徴もメッセージも確認されない。 まさにスペース・オデッセィな事件だ。 一体いつ、誰が、何の目的で立てたのか、果たしてこれは異星人から人類に対するメッセージなのか。 というのは、まあお約束のコメント。 実際は、世界各地の物好きがネットでニュースを見て真似をしているだけのようだ。 コロナ禍での暇潰しに笑えるニュースを提供したかったのか、あるいはこの苦境の解決に異星人の知恵を借りたいと願っているのか。 多分、実際の異星人が目にしたら『何やってんだアイツら』と思うことだろう。 うっかり観光地になると感染が拡大しそうで心配だ。 [一日三報]
[AFP] 【図解】謎の「モノリス」が出現した場所
なぜかAFPが積極的に取材を続けている。 こうして見ると割と形も素材もいい加減に作られている。 もっとも映画の「モノリス」も原作や設定と違っていたりするわけでブツブツ(以下うんちく) 日本の畑に鉄板が埋まる日も近いか。 [PR TIMES] コロナが影響 「2020年、今年販売苦戦したランキング」 口紅、鎮暈剤、総合感冒薬など化粧品、市販薬中心に行動変化が背景
年末になると話題になる「今年売れたモノランキング」。 その逆を調査した「売れなかったモノランキング」は、このご時世も相まって興味深い。 つまりこれらのモノは人間の生態的生存には何ら関係なく、とはいえ社会的生存には必死なモノだったと考えられる。 個人的には今年は服を全く買っていない。 [CNN] 人体改造受けた「超人兵士」、フランス軍倫理委が容認
今日のバイオニック・ソルジャー。 ゴルゴ13で見た。 超人兵士は憧れるけど、やっぱりちょっと怖いわけで。 近代戦争で無人戦闘を目指す理由の一つに、先進国において兵士一人にかかるコストが、かつての世界大戦と比べてめちゃくちゃ上がってしまったというのもある。 一方で某国や某国などは人間爆弾や人海戦術でドンパチするわけで。 なかなかに難しい問題です。 [今日の独言(ひとこと)]
新型コロナウィルスの感染拡大により、国民全員への完全外出禁止令が発令された日本。
オンライン会議を行っていた最中に、突然一人の社員が頭から血を流して死亡した。 当初は自殺かと思われたが、状況から見ると他殺としか思えない。 だが被害者は独身の一人暮らし、家には鍵を掛けており、おまけに外では防護服に身を包んだ警察官がパトロールを行っていた。 非常事態宣言下で発生した『社会的密室事件』。 果たして犯人は一体…… というアイデアを思いついたが、中身はまだ何も考えていない。 書かない小説家、文庫本の裏の煽り文だけは得意な私です。 仕事柄、特にオンライン会議が必要なものではないが、機会があってこの間カメラとヘッドセットを使って対面で打ち合わせをやってみた。 使用したソフトはGoogle MeetとCisco Webex Meetings。 一番名前の聞くZoomは、システムかセキュリティの都合で相手側から認められなかった。 オンライン会議については、昔Skypeでオンラインチャットを散々やっていたので特に戸惑うこともない。 あの頃に比べると操作も手軽で映像も音声も格段に精度が上がってはるかに使いやすくなっていた。 コロナ禍で今後も急速に発展していくメディアツールになるだろう。 私は昔から電話が苦手で、掛けるのも掛かってくるのも一呼吸置いてからでないと使えない性質だ。 その理由の一つに、電話中は『何でもできるのに、何もできなくてストレスを感じる』ことにあると最近になって気づいた。 電話中は耳と口を使うだけなので、目も手も足も自由になる。 しかし自由だからといって漫画を読んだり、何か手作業をしたり、移動したりすると電話の内容が全く疎かになってしまう。 その、ものどかしさに耐えられなかったようだ。 器用な人は電話をしながらテレビを観たりゲームをしたり、今はもう禁止されているが自動車の運転をしたりできる人もいる。 というか、そういう人のほうが多い。 でも私は、根がシングルタスクなのか、電話中は電話以外の何もできなくなってしまうのだ。 オンライン会議はそんな私のストレスを解決してくれるツールだと感じた。 何しろ電話中は他のことが何もできない。 目は相手の顔を見て、耳と口は相手の話を聞いて、手はペンやキーボードを使ってメモを取ることができる。 つまり落ち着いて電話に取り組むことができるのだ。 電話に苦痛を感じない人には何を言っているのか分からないかもしれないが、つまりはそういうことのようだ。 ということで、オンライン会議の波はゆるやかに作家業界にも及びつつある。 とはいえ対面したから仕事が進むというものでもないので、これからはごく当たり前に置き換わって、使われるようになるだろう。 ただ、会ったついでにちょっと遊びに行きましょう、という機会は減るかもしれない。 まあ今は、遊びに行くのも憚られるご時世だが。 [一日三報]
[AFP] チーズフォンデュは安全か? スイスで議論
日本では複数人で鍋パーティを開いた結果、感染が広まったというリアル『コロナ鍋』も起きているらしいが。 所変われば、彼の地は彼の地で、割と深刻な話題だと思う。 結局の所コロナ対策としては、外へ出るな、一人でいろ、何もするな、に勝る有効な手段はないわけで。 心配ならやるなとしか言いようがないと思う。 でも、チーズフォンデュの熱でウィルスも死滅する、は見当違いの意見ではないかと。 [CNN] 村名を「フッギング」に改称、性的な冗談にされ住民うんざり オーストリア
英語の「ファッキン」は日本語で言う「クソ」に近い意味を持つ。 直訳すると「性交」になるが、使い方によっては全く別の意味となる。 日本語の「クソ」もそのままだと大便の意味だが、「クソ野郎」と排泄物とは何の関係もない。 なかなか的を射た翻訳だと思う。 それはともかく、ネタにされるの嫌だから村の名前を変えるとか、どこでも似たようなケースとクソ野郎がいるものです。 エロマンガ島。 [47NEWS] 日本人捕虜が「時間つぶし」に制作した美術品
これもまた戦争の犠牲者。 過酷な環境でも、過酷な環境だからこそ、芸術性を止めることはできないものか。 やっぱり芸術はまず平和ありきでなければならないと思う。 [今日の独言(ひとこと)]
鹿児島県から沖縄県にかけて広がる南西諸島で、国内で35年ぶりとなる新種のゴキブリが2種発見された。
本種は体表に暗青色の光沢を持つルリゴキブリ属の一種で、それぞれ「アカボシルリゴキブリ」「ウスオビルリゴキブリ」と名付けられたそうだ。 国内、新種、35年ぶりとなると結構なビッグニュースだが、当然ながらこの発見はほとんどの報道機関から無視された。 理由はもちろんゴキブリだからだろう。 もしこれが希少な野鳥や、色鮮やかなアゲハチョウだったら盛んに喧伝されて、発見地には施設やマスコットキャラクターまで作られたかもしれない。 しかし全くそんな動きが見られないのは、やはりゴキブリだからだろう。 世間ではゴキブリの写真はおろか、この四文字すら見たくないという人も多い。 かく言う私も心の底から大嫌いで、その恐れはもはや前世からの因縁を予感させるほどだ。 そもそも虫の類いは全て苦手で、それがどうして苦手なのかを追求した結果、『昆虫部』と『バジリスク -寄生生物-』という二つの小説を書いてしまったほどだ。 おかげで昆虫好きと誤解を受ける羽目にもなってしまった。 人はなぜゴキブリをそれほどまでに嫌うのだろうか。 いや、現代日本人の多くは、という括りにしても良いだろう。 なぜなら、かつての日本人はそこまで嫌っておらず、『御器かぶり』の由来にもあるように日常生活の一部になっていた。 また特に多く生息する東南アジアの人々もそこまで嫌悪していないからだ。 興味深いことに、ヨーロッパでは『ヘビ恐怖症』や『クモ恐怖症』というものがあり、その理由を真剣に研究している学者もいる。 ところが私を含めて多くの人はそこまでの恐怖症は抱いていない。 クモはまだしも、ヘビなどは神社にも祀られて干支の一つにも選ばれている。 つぶらな瞳とくねくねした動きが可愛いと感じる人も少なくはないだろう。 ヨーロッパの研究者は、これは毒ヘビや毒グモを恐れる人類の本能に起因しているという説も出しているが、正直言ってピンと来ない。 それでは毒を持たないゴキブリに対する恐怖症はどうなるのかと尋ねたい気持ちだ。 畢竟、この恐怖症は人の生活圏、特に家屋内に侵入することに起因している。 つまり安全なプライベート空間に現れることにより、まるで体内にまで侵入されたような嫌悪感を覚えるのだろう。 家の中に現れるなら、ヘビもゴキブリもカブトムシも怖くて気持ち悪い。 これが密閉率の高い近代的な家屋と、衛生意識の高い現代人の感覚から完全に敵として認識されるようになり、耐えがたい忌避感をもららしてしまう。 私はそのように結論づけた。 逆に言うと、人間が自ら家屋への侵入を許し、あまつさえ抱き締めて頬を寄せることすら厭わない、ペットの犬や猫というのは奇跡の動物とも言えるだろう。 と、可愛い話で締めておく。 [一日三報]
[AFP] 米砂漠で謎の「モノリス」発見 正体めぐり奇説飛び交う
[AFP] 今度は消えた? 米砂漠で発見の謎のモノリス 地元当局が現地写真投稿 今日のコズミック。 2001年も遠くなり、宇宙の旅も現実になりつつある昨今、それでも人々は宇宙オカルトが大好きな模様。 果たしてこのモノリスは宇宙に住む知的生命体からコロナ禍に喘ぐ地球人に向けたメッセージなのか。 実際は誰かが仕掛けた、つまらない現実をちょっとでも忘れさせるためのジョークだと思う。 [時事通信] かぜ薬、65%が誤解 ウイルス倒さず、正しく服用を
今日のマッチポンプ。 あれだけ「やっつける感」のあるCMを流しておきながら、「正しく服用を」と語る傲岸不遜。 どうせなら薬剤の重みでウィルスを押し潰しますくらい言ってはどうか。 でも呪いや毒のせいにしないだけでも、みんな正しい知識を身に付けているかと。 こまけぇことはいいんだよ。 [CNN] 英辞書が選ぶ今年の単語は「ロックダウン」、もとは刑務所用語
[オリコン] 今年の“新語”大賞は「ぴえん」 新型コロナ関連のワードも続々トップ10入り どちらも辞書・辞典の会社が主催しているが、この温度差たるや。 ナポレオンの失敗は、辞書に不可能の文字を入れておかなかったことにあると思う。
|
||||