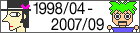|
|
||
| archive
|
[今日の独言(ひとこと)]
----------------------------------
初めまして。椙本と申します。 メールマガジンの登録を行って頂き誠にありがとうございます。 今回は第1号という事もあって、少し長めに書かせて頂きました。 お時間の余裕があります時に一気に読んで頂ければと思います。 って、ここで書いてちゃ意味無いですね。 (2003年3月19日 Vol.01) ---------------------------------- この度ついに当メールマガジンが1000回目の配信を迎えることとなりました。 2003年3月19日の第1回配信から18年……18年!? これも偏に、ぼちぼちと配信を受け取りいただいてきた皆様のお陰です。 あらためて厚く、厚く御礼申し上げます。 人間は人それぞれ、色々な才能があります。 なくて七才、あって四十八才。 運動なのか勉強なのか、理数系か文学系か、商売か犯罪か。 その中でも私は多分、継続の才能が他人より少しあるように思えてきました。 メールマガジンもそう、毎日のラジオ体操もそう。 一冊10万字、300ページの小説を書くのも、結局のところ継続です。 この才能は非常に目立たず、当然ながら子供の頃には判別できません。 十年、数十年経ってから、そう言えばそうなのかもと、自身でも気づくものでしょう。 継続のコツは結局のところ、好きなことを無理なく続けることだと思います。 この「無理なく」というところが非常に難しい。 大体の人は好きだからこそ無理をしてしまう。 プリンを一口だけ食べて、残りはまた明日とできるか。 できる人には継続の才能があるでしょう。 私なら十個買って毎日食べます。 1000回を迎えた記念に、というわけでもないですが、ちょうど良い機会となったので新刊の告知をこっそりしておきます。 ---------------------------------- 【新刊】 『フィニッシュライン 警視庁「五輪」特警本部・足利義松の疾走』 2021年6月5日発売予定 出版社:潮出版社 価 格:935円(税込) ---------------------------------- なんと、去年にお蔵入りとなっていた東京オリンピックの小説を出版していただけることになりました。 この時期に! このタイミングで! この内容で! まさに奇跡のような作品です! 多分、日本中の小説家を探しても、今、東京オリンピックの小説を出せるのは私だけでしょう。 まだ一か月先なので、これからぼちぼちと内容を明かしていくつもりです。 どうぞお楽しみに。 他にも色々と活動しているのですが、なかなか言い出しにくい感じになっています。 でもタイミングが来たらちゃんと告知させていただきます。 メールマガジンはこれからも低空飛行でぼちぼちと続けて参ります。 多分2000号までは続けないので、これまで通りお付き合い頂けたら幸いです。 [一日三報]
[ロイター] 「心の霧」と闘うスペインのコロナ後遺症患者たち
いよいよコロナ後遺症の問題も現れ始めた模様。 ただ、こういった症状がコロナ特有のものか、他の一般的な風邪の後遺症として起っているものなのか分からない。 安易にとらえてはいけないが、過度に心配しなければならないのか。 その分からなさも新しい病気の特徴なのだろう。 [CNN] 手のひらかざして支払い完了、米スーパーが新方式を導入
便利そうにも見えるけど、「手首切り強盗」が現れないかとちょっと不安。 それはともかくアマゾンやグーグルは、そろそろクローン人間も作れるんじゃないかと。 [Newsweek] 「アジア人は禿げない」神話に異変 東アジアで薄毛化加速、中国では20年早まる
そんな神話があるのかと驚き。 でも確かに白人の中年はハゲがデフォルトのような気もしたり。 中国はそろそろ育毛、発毛、ヅラブームが起きると予感。 もう起きているかも知れないけど。 昔「101」って中国の発毛剤があったね。 [今日の独言(ひとこと)]
名言には不変の名言と固有の名言がある。
不変の名言とは、言葉自体が不変的なもので、いつ、誰が使用しても名言となる言葉だ。 一方で固有の名言とは、言葉自体は名言に値しないが、特定の時、場所、人物が使用したことで名言へと昇格した言葉のことだ。 『人生はすべて、次の2つから成り立っている。したいけど、できない。できるけど、したくない』 これは皆さんご存じの名言メーカー、ゲーテの名言だが、別にゲーテが言ったと知らなくても不変の名言になる。 『時間がやわらげてくれるような悲しみは何一つない』 は、キケロの名言だが、これもいつ誰が言ったとしても不変の名言だろう。 大体キケロは紀元前ローマ時代の政治家であり、何をした人かを知っている人も少ないだろう。 一方で固有の名言とは、 『そこに山があるから』 と言った登山家ジョージ・マロリーの名言や、 『握り拳と握手はできない』 と言ったマハトマ・ガンジーの名言などがある。 当たり前のことでも言う人によっては名言に聞こえるので固有の名言ということだ。 その中でも世界一有名な固有の名言となると、聖書の言葉になるかもしれない。 『求めよ、されば与えられん』 『探せよ、されば見つからん 『叩けよ、されば開かれん』 ちなみに本を英語にしたBOOKの語源は、聖書のBIBLEだ。 今年は人類初の宇宙飛行から60周年を迎えた。 人類初の宇宙飛行士ガガーリンは、初めて宇宙から地球を眺めて『地球は青かった』という不朽の名言を残した。 これなどガガーリンだからこそ成り立った名言であり、ガガーリンでなければ小学生の感想になっただろう。 そんな固有の名言で一番の成果を残したのは、相田みつをかもしれない。 どんな言葉でも『みつを』と付けると名言っぽく聞こえるのは、『みつをイコール名言』の公式が擦り込まれているからだろう。 相田みつをさんが他に何をされていたのかよく知らないのも特徴的だろう。 なお、それとともに、言葉単体でも名言だが、発言者を加えることによってより名言の力が高まる『ハイブリッド・名言』というのもある。 『墓場で1番の金持ちになってもしょうがない。夜眠る時、我々は素晴らしいことをしたと言えることが大切だ』 『たとえ明日、世界が滅亡しようとも、今日、私はリンゴの木を植える』 上はスティーブ・ジョブズ、下はマルティン・ルターの名言だ。 言葉だけでも納得だが、発言者を知っていればさらに理解が深まる。 世の名言者が目指すところはその地位だろう。 これが、何百首と名言を見てきた私の研究結果である。 [一日三報]
[中央日報] 「遺体が必要」富裕層の依頼に生きている人を拉致し火葬…中国社会に衝撃
ともすればミステリ小説のネタにも使えそうな興味深い事件。 文化の違いというか、死生観の違いが動機となっている。 なお日本の火葬文化は仏教の影響が強く、神道は土葬にして古墳を作るのが習わしだった。 キリスト教やイスラム教といったアブラハム系も土葬がメインな訳で、むしろ火葬のほうが珍しいのだろう。 [ITmedia] しまむら「テレビCMをゼロへ」 ネット広告との“信頼感の逆転現象”
お陰でネットにも図々しいCMが増えたわけで。 テレビCMのほうでもネットを意識した作り込みが増えてきた気がする。 CMや広告がなければもっと清潔で使いやすい世界が訪れると思うのだが、無料である限りそうもいかないのかな。 [ナショジオ] ゴリラはなぜ胸を叩くのか? その音からわかったこと
まず一行目の、ゴリラの胸叩きが「キングコング」によって世間に知られるようになったこと。 そんな歴史があったのか。 動物は人間よりも無駄な争いを避ける術に長けていると思う。 ややこしい人がオラオラ言うのも野生によるものかもしれない。 [今日の独言(ひとこと)]
今でも時々、家の前を廃品回収のトラックが通りがかる。
チューニングなどお構いなしの大音量で『ご家庭内でご不要になりました、古新聞、古雑誌、古着など、ございましたら……』という定番の文句が耳に届く。 ただ、そこにちょっと違和感を覚えた。 全国共通はどうかは知らないが、昔聞いた音声には『古新聞、古雑誌、ボロ、古着など、ございましたら……』と言っていた。 いつの間にか、ボロがなくなっている。 ボロは引き取らなくなったのだろうか? そういえば近頃は、ボロという言葉も聞かなくなった。 いや、ボロとはそもそも何だ? 今さらながら、そんなどうでもいいことが気になってきた。 ボロとはおおよその予想通り、ボロボロの布のことだ。 ただし単なる屑切れではなく、縫い合わせて継ぎ接ぎだらけになった古着のことをそう呼んでいた。 ボロボロの古着だからボロと言う。 ところが、『ぼろ』と入力して漢字変換すると『襤褸』という、やたらと難しい漢字が現れる。 どう見てもボロとは読めないだろう。 これは日本語ではお馴染みの熟語訓というものに違いない。 熟語訓とは、漢字を単語ではなく熟語の単位で訓読みを与えたものだ。 『昨日』と書いて『きのう』、『商人』と書いて『あきんど』。 『本気』と書いて『まじ』と読むのも熟語訓だ。 意味を調べると『襤褸』とは「らんる」と読み、継ぎ接ぎだらけの古着を示していた。 古くは797年に空海が書いた『三教指帰』に『ぼろぼろの服』という意味で『濫縷之袍』(偏が違う)という言葉が登場する。 さらに古くは中国の前漢時代(紀元前206年-8年)に揚雄撰という人物が書いた『揚子方言』という書物に同じ意味で登場していた。 なお『ボロ』という擬態語がいつ現れたのかは、調べてもはっきりしなかった。 ただボロボロのボロとして民間で自然と広まった言葉なのだと思う。 それを恐らくどこかの偉い人が、世間で言うボロとはつまり襤褸のことだと伝えて広めたのだろう。 そして現代ではボロを来ている人も少なくなったので、廃品回収の文言からも消されたようだ。 『ボロを着てても心は錦』『外襤褸の内錦』という言葉もある。 今となっては襤褸も錦もいちいち説明しないと伝わらないだろう。 ちなみに競馬や馬牧場の業界用語で『ボロ』と言えば『馬糞』を意味する。 馬は糞をボロボロと落とすことからそう言われるようになったそうだ。 [一日三報]
[ITmedia] Neuralink、脳にチップを埋めたサルが「Pong」を思念でプレイする動画を公開
[AFP] 共犯は「サル」 強盗させた男2人逮捕 インド 今日のおサルさん。 昔、宇宙人もこうやって人類を生み出したのだろうか。 やがて我々が宇宙で暮らすようになると、彼らが次に地球を統べるようになるかもしれない。 [CNN] 過去1200年で最も早かった日本の桜、生態系脅かす気候変動の兆候と専門家
これもある意味、異常気象。 その内いつもフライング気味の24節気72候も、ぴったり収まるようになるかも。 暦の上ではもう春ですが、やっぱり春です。 [読売新聞] パソコンやゲーム、使用長ければ「夜型」小学生に…「3時間以上」でリスク1・7倍
昔、NTTはテレホーダイという、深夜時間には定額料金で電話がかけ放題になるプランがあった。 インターネットの黎明期、まだ通信料金が接続時間によって加算されていた時代、このプランに目を付けた者たちがこぞって深夜時間のみネットに接続するようになった。 私が宵っ張りになったのは間違いなくその影響だ。 [今日の独言(ひとこと)]
先ごろ、『現代人はなぜ虫が嫌いになったのか』を調査した東京大学の研究グループがその結果を同学のホームページ上で発表した。
それによると虫嫌いについては二つの要因が重なっているものとして、一つには『都市化によって屋外で虫を見る機会が少なくなった一方で、屋内でよく見られるようになり、病原体を回避する心理から強烈な嫌悪感を持つようになった』。 もう一つは『自然で虫に触れる機会が少なくなったことで虫の区別が付かなくなり、無毒無害な昆虫も含めて全て嫌悪するようになった』と結論づけていた。 つまり『虫は病原体を運びかねない不潔な生物であるから近づけてはいけない』という知識と、『虫の違いが分からない』という未知の恐怖が虫嫌いを増やしているようだ。 【参照】なぜ現代人には虫嫌いが多いのか? ─進化心理学に基づいた新仮説の提案と検証─ | 東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部 人間は未知なる物に対して、多大なる興味を抱く一方で、底知れない恐怖も感じずにはいられない。 その恐怖とはつまり『身の危険』に起因する本能のものだろう。 地上の全てを支配し、敵対するものなど何もいなくなった人類も未知の生物に対する恐怖は拭えない。 むしろ無敵であるがゆえに未知に対して過剰に反応してしまう面もあるのだろう。 これは人間同士の差別に対しても同じことが言えるかも知れない。 人種差別や国籍差別というのも『危険』『信用できない』という大まかな知識と『未知』ゆえの恐怖から敵対心を持ってしまうのだろう。 アメリカの白色人種の人から『黄色人種が新型コロナウィルスを世界に広めた』と言われて差別を受けてもどうしようもない。 『日本人は賢くて勤勉で礼儀正しく心優しい』と言われても、いや人それぞれだろうと思う。 相手が昆虫でも人間でも、人の心理は似たようなものなのだ。 ゆえに、差別に対する手段は相手に正しい知識を得てもらう以外にない。 昆虫も正しい知識を持っていればそこまで嫌悪することもなくなるだろう。 ただし、そもそも嫌いな相手のことを知ろうとする人などあまりいない。 やはりなかなか難しい問題だ。 [一日三報]
[AFP] 洞窟で閉じこもり実験「ディープタイム」 時計なしで6週間 フランス
6週間後、血みどろの人間がたった一人だけ現れたりして。 でもそれくらいなら割とエンジョイできそうな気もしたり。 清潔にしておいてもらえたら。 [NHK] 12年間の山ごもり修行を満行 比叡山延暦寺で20年ぶり
洞窟で6週間は知らないが、こちらはもっと過酷。 山で過ごすだけと思われそうだが、実際にはびっしりと修行のスケジュールが組まれており、毎日ひたすら山を歩き回って、粗食に耐えて生き続けなければならない体力勝負の面も大きいようだ。 [ロイター] 米マイクロソフト、陸軍からARヘッドセット受注 219億ドル相当
海外は官民、大っぴらに軍事研究・開発ができて良い。 その技術がそのうち一般消費者にも回ってくるかも。 ゴーグル・マスクで街行く日も近い。 |
|
|
|
||