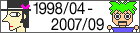|
|
||
| archive
|
[今日の独言(ひとこと)]
民放テレビの視聴者がネットフリックスやアマゾンプライムなどの有料配信動画サービスに流れて、YouTubeなどの個人制作の動画も手元のスマホでダラ見するようになった昨今、長らくメディアの王として君臨してきたテレビの地位は大きく下がり続けている。
とはいえテレビの価値はまだまだ高く、完全に落ちきるまでには至っていない。 テレビの価値とは、居間の一角を占有し続けている大画面、行政をはじめとした社会との繋がり、長年にわたって根付かせてきた生活スタイル、豊富な資金力と有名俳優を起用できること、そして24時間連続で放映できることだろう。(深夜は放送終了するが) 特に24時間365日、番組を放映できる形態は、好きな時に好きな番組を視聴できる新メディアへの対抗手段として唯一残されている強みかもしれない。 世の中にはとりあえずテレビを点けておくという人も少なくないからだ。 衛星放送のBSに「釣りビジョン」というチャンネルがある。 名前の通り釣りに関する番組だけを放映している専門チャンネルだ。 私は寝室にテレビがあるので、眠るまでの時間を何気なく観ているが、これがなかなか面白い。 なにせ、いつ点けても必ず釣りをしているからだ。 春夏秋冬、海釣り川釣り、朝釣り夜釣り、サオだルアーだエサだと手を変え品を変えて、よくもこれだけやることがあるものだと感心させられるのだ。 しかし本当に釣りだけで24時間365日、番組をやってると、いかに視聴者が釣り好きでも見飽きてしまう。 そこで有名な釣り好き芸能人を起用したり、若い女性を釣り人に仕立て上げたり、それこそYouTuberとコラボを行ったりもしている。 YouTuberを扱う際には番組の構成や演出もYouTubeっぽく見せるているから芸が細かい。 それでも番組が足りなくなると、釣った魚を調理したり、旅には欠かせない道の駅なども紹介したりしている。 さらには港にヨガマットを敷いて女性にヨガをレクチャーしながら釣りとも絡める変則番組も行っている。 そして極めつけは、釣り人の間で噂になっている心霊スポット巡りなども番組にしていた。 もはや魚はおろかサオの一本すらも出てこない。 謎の霊能力者が二人の女性を連れて、「そこにいる!」だの「足が痛む」だのとギャアギャア騒いでいた。 24時間365日テレビ番組を作り続けろ、内容は自由、ただし必ず釣りを絡めろ。 そんなルールの下で一体何が思いつけるか、どんな番組が作れるかと日夜挑み続けているのが面白い。 というわけでBSの「釣りビジョン」はなかなかお薦めです。 釣りに全く興味のない私が言うのだから間違いありません。 [一日三報] [毎日新聞] ジョン・レノンの音声テープに650万円 未発表曲など収録
どこかの短編小説に、そんなサギの話があった気がする。 650万円で売れるならいくらでも不正ができそうな気もするが、正式なものなのだろうか。 そして購入者はより高い値段でレコード会社に売り込み、数年後には未発表曲としてリリースされるのかもしれない。 [Gigazine] カンニング防止のため地域一帯のインターネットが遮断される事態に
数年前にも同じ地域で同じ話が上がっていたかと。 これからはスポットのWi-fiの代わりに、スポット遮断の商品が現れるかも。 デジタルデトックスにもお薦めとか。 [ITmedia] 頬を膨らませてマウスをクリック ハンズフリー操作可能なマスク型デバイス
今時のテクノロジー。 賢い人は社会の逆境からも新たな発想が得られる。 ついでに舌先の位置から文字入力をできると面白いかも。 マスクの中はもうベロンベロンよ。 [今日の独言(ひとこと)]
ホラー映画13本を見たら1300ドル(約14万円)の報酬を支払うと、アメリカの会社がそんな計画を発表した。
金融会社のファイナンスバズが「ホラー映画心拍数アナリスト」として、映画を見た際の心拍数の変化を測れるユーザーを募集している。 「高予算のホラー映画が低予算の映画よりも強い恐怖を与えるのかを把握したい」といのが目的だそうだ。 なお対象となる作品は「ソウ」「悪魔の棲む家」「クワイエット・プレイス」「クワイエット・プレイス 破られた沈黙」「キャンディマン」「インシディアス」「ブレア・ウィッチ・プロジェクト」「フッテージ」「ゲット・アウト」「パージ」「ハロウィン(2018)」「パラノーマル・アクティビティ」「アナベル 死霊館の人形」の13作品だ。 ようやく私の趣味が活かせる時が来たかと思ったが、なんとなく胡散臭い話にも思える。 制作費の高さがホラー映画の怖さに比例しているはずもなく、結局はストーリーと演出にかかっているのは分かりきっている。 制作費はあくまで有名俳優の起用やセットや撮影機材の大規模化、宣伝費用など「背景」の選択肢を増やすことに費やされる。 これはホラーにかかわらず全ての映画に共通していることだろう。 ちなみにこの13作品の中で一番低予算で制作されたのは、恐らく「パラノーマル・アクティビティ」だろう。 1万5000ドル(約165万円)の制作費で、1億9300万ドル(約210億円)の収益を出したことで話題になっていた。 ということで、これは単に自社の宣伝目的で発表しただけの企画なのだと思う。 アメリカはよくそういう手法でモニター募集を行っている気がする。 ホラー好きとしては、この企画に選ばれた被験者に予想外の恐怖が襲いかかるという展開を期待したいところだが。 さらにそこからドキュメント風ホラー映画を制作して欲しいところだが。 [一日三報] [ITmedia] Facebookのスマートグラス「Ray-Ban Stories」発売
今日のサイグラス。 レイバンのサングラスがひたすら胡散臭いことを無視すれば、スマートメガネ業界も一歩前進したことになるか。 メガネ撮影による盗撮問題も、そろそろ自己防衛の面で認められる社会が来る気もしている。 [読売新聞]「知らない人の名前書かれたメモ」が車のワイパーに…巡査が別件の個人情報挟むミス
ミステリかホラー小説にありそうな設定。 結局、情報ってこういう人的ミスから流出していくんだろうね。 [朝日新聞] 落差181メートル、「九州最大級」の滝確認 奄美市が名前を募集
Googleマップでも普通に確認できる滝でした。 滝があるのは知っていたいが、そこまでとは思っていなかったという感じだろうか。 網羅したと思われている中にも、詳しく調べてみれば実は世界最大、最長、最高の自然が隠されているのかもしれない。 富士山よりも奈良の若草山のほうが高い可能性もある。 名前からしてもう低そうだけど。 [今日の独言(ひとこと)]
インターネットの情報は、面白いけど当てにならない。
Wikipediaの記事も90パーセントは正確だと思うが、10パーセントほど虚偽が混じっているようなので、なかなか参考文献としては扱いにくい。 とはいえ図書館へ行って資料を集めたり、人を訪ね回ったりするのも大変なので、Wikipediaでおおよその知識を得た上で、ピンポイントで正解を探るのが良いだろう。 医学や歴史に関しての調べ物は、そういう感じで行っている。 先日のニュースによると、平成29年に東名高速道路であおり運転を受けた夫婦が死亡した事故をめぐり、ネット上に無関係の建設会社の情報を書き込んでデマを広めた54歳の男が名誉毀損罪で罰金刑が確定した。 男は当時、事故を起こした男の勤務先として「これ?違うかな」という言葉とともに北九州市の会社の情報が記載されたホームページのURLを投稿していた。 ニュースを見て、ああ、あの事件かと思った人も多いだろう。 私も目にした覚えがあるので相当広まっていたと思う。 私自身は全く関係ないので気にしなかったが、誤解を受けた会社はデマを信じた「正義の味方たち」から連日お叱りの電話が鳴り止まず大変だったらしい。 電話をかけた人たちも今ごろ戦々恐々としているかと想像したが、多分俺は何も間違っていないと開き直っていることだろう。 それくらいの根性でなければ苦情の電話など入れないはずだ。 ただ一方で、この程度のことで罪を受けるのかという驚きもあった。 やったことは悪質で何も擁護できないが、「これ?違うかな」として無関係な情報を出すような手法は、新聞や雑誌でもままあることだと思うからだ。 虚偽ではなく、誤認を誘う手法は程度の低い広告の常套句でもある。 しかも裁判の結果を見る限り、この犯人は何か別の目的でこの会社を貶めようとした訳でもなく、どこからか金銭を受け取っていたようなこともなかったらしい。 本当に、単にこれじゃない? と思って書き込んだだけのようだ。 「口は災いの元」を地で行くような話だが、結構重要な問題に思える。 デマを広めるメディア、マスコミと、この犯人との違いはどこにあるのだろうかと思った。 最初の文で「Wikipediaの記事も90パーセントは正確だと思うが、10パーセントほど虚偽が混じっている」と書いたが、これも特に検証した訳ではなく、何となくそんな感じに見えるというだけの話だ。 しかし、これもあるいはデマを広めて名誉を毀損させたとして訴えられるかもしれない。 これからは余計なことはネットにも書き込まず、心に留めておくのが良い時代なのだろう。 もう「王様の耳はロバの耳」ではなくなったのだ。 [一日三報] [CNN] ラッパー、額に埋め込んだダイヤを引き剥がされる 26億円相当
今日のアベンジャーズ。 なんか前にそんなニュースを見た覚えがあるわけで。 何というか、ゴールド・ロジャーに言われるまでもなく、奪えという状況だったので、おおむねその通りに事が運んだだけではないだろうかと。 ビームくらい出せたら良かったのにね。 [河北新報] 昆虫にも「楽天家」 東北大研究グループ、ハエの学習行動から解明
私はGABAのチョコレートを食べてやる気を出した人は見たことがないし、あれでやる気を出したらそれはそれで成分的にちょっと怖いと思う。 それはともかく、生き物は基本的に楽観的でサボる性質を持っているので、そこに罪悪感を抱くのは間違いなんだろうなと思う。 [女性自身] 山形の田んぼにポツンと…入居者語る“日本一安いタワマン”の意外な利点
今さらだけど「女性自身」って凄い雑誌名だ。 何かのボーダーラインに引っかかったりはしないのだろうか。 タワマンの利点は別に意外でもなんでもなく。 過疎化と高齢化が進むと、将来的にはどこもこうなっていくのではないだろうか。 まるで巨大な墓石のように。 [今日の独言(ひとこと)]
インターネット世界での「検索」は、なぜ「虫眼鏡マーク」なのだろう。
パソコンやスマートフォンでインターネットを閲覧していると、必ずどこかで見かける虫眼鏡マーク。 言語が分からなくても虫眼鏡マークがあれば、それが何かしらの検索ツールであることが分かる。 しかしよく考えてみれば「検索」に対して「虫眼鏡マーク」は繋がっていそうで繋がっていないモチーフだ。 そもそも虫を観察するための眼鏡だから虫眼鏡だ。 英語でも Magnifying glass といって、これは「拡大鏡」の意味になる。 いずれにせよ、細かい物をよく調べるための道具であり、特定の語句を調べる「検索」とは何の関係もない。 「検索」をアイコンにするなら、たとえば「辞書を引く」という意味で分厚い本のマークにするとか、「詳しく尋ねる」という意味で耳のマークにしても良かっただろう。 「検索」がなぜ「虫眼鏡」のマークなのか、それこそインターネットを使って検索してみたところ、Keith Ohlfsというデザイナーが考案したものと分かった。 氏が1987年に、NeXTのオペレーティングシステム用にデザインしたのが最初のようだ。 当初はカラーピッカー、画像を処理する作業の際に色パレットから特定の色を抽出するためのアイコンとして考案されたが、その後パソコン内から特定のファイルを選ぶ際のマークとしても転用されたらしい。 既にカラーピッカーとして馴染みがあり、双眼鏡や図書館員や望遠鏡よりも都合が良かったとコメントしているようだ。 なおNeXTというのはご存じの通り、創業者でありながらAppleを放逐されたスティーブ・ジョブズが新たに起業したパソコンメーカーだった。 ジョブズがこのNeXTをAppleに売却するとともに自身もAppleに復帰し、後にNeXTの技術を活用してiMacやMacBookやiPhoneなどの大ヒット製品を生み出した。 つまり「検索」の「虫眼鏡マーク」もまたスティーブ・ジョブズが世に広めたと言えるだろう。 ちなみにAppleといえば、かつてのMac OS 8.5時代からローカルディスク内とインターネット検索を同じインタフェースで行えるSherlock(シャーロック)というツールがあった。 由来はおなじみシャーロック・ホームズで、アイコンもホームズにちなんで虫眼鏡と鹿打ち帽(チェック柄の丸い帽子)だった。 シャレが利いていて好きだったがMac OS X v10.4で廃止となったようだ。 [一日三報]
[Gigazine] なぜハイパーリンクは青色で表示されるのか?
これもいつの間にやら普及したデザイン。 一時は青色がうざいということでリンクも黒色にするのが流行っていたが、近頃はまた青色が定番となっているようだ。 リンクを付けまくると青色だらけになるのがやや難点かと。 [CNN] タイ戦で「つり目」のしぐさ、セルビア人バレーボール選手に出場停止処分
ちょくちょく聞かれる話題だが、みんなそんなに気にしていることだろうか。 ちなみに白人さんに「鼻が高い」「鼻がでかい」も今や差別に繋がるので使わないほうが良い。 昔のコントみたいに金髪鼻高のガイジンを出すのも良くないそうだ。 そういえば「おそ松くん」の「イヤミ」はおフランスかぶれだが、ビジュアルは細目で出歯の典型的な日本人像をしている。 これが金髪碧眼の似非フランス人だったら差別と騒がれたかもしれないが、日本の漫画家が日本の人たちに向けた自虐的日本人のビジュアルなので誰も文句を言わないのだろう。 赤塚不二夫はギャグのバランス感覚も抜群だったのだ。 たまにバランスを崩して皆殺しにすることもあったが。 [ITmedia] 政府統一Webサイト、暫定版を12月までに公開 製作事業者決定
がんばれみんなのデジタル庁。 なんか20年くらい前からこんなことばかりしているような気もしたり。 とりあえずトップページを統一させたりするのだろうか。 落札額7000万円はサイト制作だけなら高額だが、事業としては有り得ないほど安すぎないかと。 そういやインターネット博覧会、通称「インパク」ってどうなったっけ? あれ100億円くらいかけてなかった? |
|
|
|
||