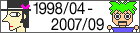|
|
||
| archive
|
[今日の独言(ひとこと)] モザイク除去は真実を隠す
先日18日、京都府警は人工知能(AI)を使ってアダルトビデオのモザイクを除去したなどとして、著作権法違反とわいせつ電磁的記録記録媒体陳列の疑いで、兵庫県の自称画像クリエーターを逮捕したというニュースが報道された。
当容疑による逮捕は全国初で海外でも見聞きした覚えはない。 行為も珍しければ『わいせつ電磁的記録記録媒体陳列』という容疑も初耳だ。 記録記録も重複間違いではないようだ。 アダルトビデオのモザイク除去といえば昭和男子の憧れワードだが、技術としてはTecoGAN(テコガン)と呼ばれるAI技術を悪用したらしい。 GAN、あるいはGANsというのは「敵対的生成ネットワーク」という意味で、今回でいうとモザイク化された部分に対してAIが適切な画像を生成し、その可否を繰り返すことによってより精度を高めて完成させる手法のようだ。 つまりモザイクを取り除くのではなく、隠された部分を新たに作り出すもので、生成された画像、映像は撮影された実像そのものではない。 ただしその精度は極めて高いということになるのだ。 近頃では同じような技術を用いて、古い画像や映像を高精細化して現代に蘇らせる試みが多く行われている。 存在しないデータは再現できないというのは、もはや古い考えとなり、AIを使えば存在しない過去を補うこともできるようになってきた。 しかし存在しないものを作り出す技術というのは悪用の幅を広げることにもなりかねない。 先のモザイク除去もその一つだが、画像や映像に存在していた人物や風景を消すことも、逆に出現させることも可能となるだろう。 ソビエト連邦の独裁者スターリンの時代では、写真から不要な人物を消す加工が盛んに行われていたようだが、それもいずれは簡単かつ高精度に行える、というか、すでに行われているのかもしれない。 いずれネットに流れている画像や動画も真実とは見なされないようになるだろう。 というわけで、選挙の候補者は今日も街頭に立って演説し握手しようと手を伸ばしている。 結局それが一番効果的な選挙運動となってしまうのも虚しい話だ。 [一日三報] [読売新聞] ヤフーニュース、中傷多いコメント欄をAI判断で非表示に…繰り返す違反者には警告
コメント欄を無くせば良いだろ思うが、そういうつもりはないらしい。 きっとコメント付けたくて記事を読む人が多いことを知っているのだろう。 ツイッターにしてもそうだが、皆さん世の中の出来事には何かと口を挟みたくなるらしい。 個人的には怨嗟と嫉妬を混ぜたコメントの窯が、ぐつぐつと煮えているようであまりいい気はしないのだが。 ガス抜きみたいな役目もあるのかも。 [AFP] 墓掘り人のもう一つの顔は哲学者 ニーチェがコロナ禍の助けに ブラジル
人生は墓掘りに似ている、というか、大体何にでも似ている。 誰しも心に哲学というか、一家言を持っているものです。 火葬場の職員さんとかも色々と思うことがありそうだけど、あまり表に出て来ないよね。 経験談とか、きっと興味深いと思う。 [CNN] 超リアルな看護師ロボット、グレースに会う 香港
コロナ騒動で注目が高まるかと思ったが、結局まあいいかで大して進展しないのかも。 普及するとすれば看護師よりも介護現場のほうが先か。 ロボット看護師さんに最期を看取られるのも、感慨深くて良いと思う。 [今日の独言(ひとこと)]
「やさしいカーナビ」という提案 私が住む奈良の町はとても良いところだが、人口が少ないせいか遺跡が多いせいか、大都市に比べて交通の便にはやや難がある。
町々を繋げる路線は細く数も少なく、バスも充実しているとは言えず夜も早い。 結果、県民は自家用車を足代わりにすることが多く、それもまた交通機関の不足にも繋がっているのだ。 それで自動車を日常的に運転しているが、目的地へ向かうためにはカーナビを活用している。 近頃は車載用のものがあまり満足に働いてくれないので、主にスマホの「Y!カーナビ」(ヤフー)をメインに使っている。 「Googleマップ」のカーナビ機能を使っても良いのだが、何度かトンチンカンな目に遭ってからはこちらを使うことにしている。 カーナビゲーションの機能としては充分、というか、これがあれば車載用のナビは必要ないとまで感じているのだ。 ただ、先に「Googleマップ」のカーナビ機能がトンチンカンと書いたが、「Y!カーナビ」にせよ従来の車載用カーナビにせよ、おかしな振る舞いをすることはよくある。 指示される道があまりに細い路地であったり、強引な右折を案内したり、行き止まりを突き抜けよと言ったりする。 町なかにある、地元民しか知らないような細い抜け道が急に混雑するようになると、実はカーナビが案内するように変更されたからという話もよくある。 現代のドライバーは「ハーメルンの笛吹き男」よろしく、経験や周囲の風景よりもナビの案内を信じてどこまでも付いていく傾向にあるのだ。 だって行けって言うんだもん。 それで、どうして強引な道案内が指示されてしまうのかというと、これは単純に「目的地へ早く到着すること」が最優先になっているからだろう。 当たり前のことだが、そのせいでどんな道であろうと、交通ルールに外れていなければ案内することになっているようだ。 しかし自動車の大きさも違えばドライバーの運転技術も様々だ。 同じ免許を持っていても、初心者もいれば高齢者もおり、到着の早さよりも走行の安全・安心を求める人も少なくはないだろう。 そもそも救急車でもないのだから、5分10分遅く到着しても何の問題もないことがほとんどだ。 多少は時間がかかっても、大きな道で無理のない走行を案内してほしい人もいるはずだ。 そんな安全で安心な道だけを選んで案内してくれる「やさしいカーナビ」があってもいいと思う。 いや、これはなかなかのアイデアではないだろうか。 [一日三報] [産経新聞] <独自>郵便局の顧客データ活用へ 総務省が来夏まで指針
今日のデジタル庁。 さらっと書いているが、『郵政グループは、郵便物の配達時の状況からリアルタイムの居住者情報や自動車の保有状況、商店の開店・閉店情報などを把握している。』の一文が恐い。 いや、まあ毎日配達しているからそれくらい把握しているだろうけど。 で、それを自動車販売会社に渡して営業に使ってもらおうというのがまた。 色々とざわつく気持ちもあるけど、それはともかく何で民営化したんだっけ? [読売新聞] ターゲット広告「ない方がよい」67%、巨大ITのデータ収集「弊害大きい」半数…読売世論調査
ちなみにこの記事を読んでいる時の私の画面はこんな感じ↓ 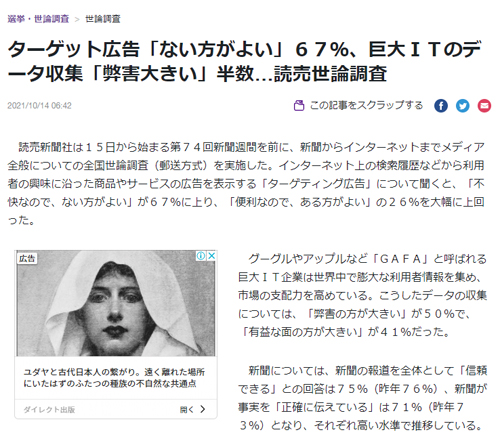 実に説得力のある記事だと思う。 だったら何とかしろよとも思う。 ちなみに古代日本人はイスラエルの「失われた十支族」の末裔で、ユダヤ人と祖先を同じくしており、言語や祭事に共通点が見られて皇族や神道とも深い繋がりがあって、つまり偉大で優秀で最強な人種なのはこの界隈では常識なので、私が今さら高い本を買ったりセミナーを受けたりして勉強する必要なんて全くないんですよ(早口)。 何でしたら一冊書きますよ、オカルト・トンデモ・カストリ本。 [Mdn] 「長寿命」はもう古い? 「自ら発電」し駆動する不思議なワイヤレスマウス「SMART R MOUSE」
今日のギリでいらないもの。 頼みのソーラーパネルがガッツリ手で隠れる所にあるのがなんとも。 でももう少し技術が上がれば、本当に無充電・自家発電が実現できるかも。 トラックボールで充電するとか、クリックの圧力で充電するとか。 使いにくそうだけど。 [今日の独言(ひとこと)]
めっちゃという言葉を、めっちゃ使う。
話し言葉でも書き言葉でも、めっちゃ使う。 小説内では話し言葉でも書き言葉でも使わない。 安っぽい流行言葉で、ふさわしくないと思っているからだ。 文化庁の調査によると「めっちゃ」や「じみに」といった言葉は現代社会に広く浸透しており、多くの人が日常会話やメールなどで使用しているらしい。 一方で「鬼○○」といった表現は少なく、どうやら廃れゆく傾向にあるようだ。 言葉というのは生き物で、使用には場を選ぶが、真に正しい言葉というものは存在しない、というのが持論だ。 しかし「すごく」が「めっちゃ」になり、「なんとなく」が「じみに」へと、一音すら合わない言葉へ変化していくのも興味深いことだ。 「めっちゃ」の由来はご存じの通り「滅茶苦茶」だが、「滅茶苦茶」の由来は「無茶苦茶」になる。 では「無茶苦茶」の由来となると、これがどうもよく分からないようだ。 インターネット上では「お茶を出さない」=「無茶」、「お茶が苦い」=「苦茶」となり、つまり「話にならない」という意味に由来する、とまことしやかに語られている。 しかしさすがにこれは稚拙な解釈で、文法の歴史的変遷にもそぐわないので真実とは思えない。 インターネットの質問コーナーでは、見知らぬ一般人が堂々と持論を正統なものと語るので信じ切れないのだ。 で、これも持論に過ぎないが、「無茶苦茶」の「苦茶」は「無茶」に合わせただけなので無視してもいい。 つまり本質は「無茶」にあり、「無茶をする」よりさらに強い意味を持たせるために「無茶苦茶をする」と言い出したの発端だろう。 そして「無茶」の由来は仏教用語の「無作」(むさ)、無為自然、人が手を加えていない様と言われている。 「無作」がなまって「無茶」となり、「無茶」がパワーアップして「滅茶」となり、さらにリズムを持たせて「めっちゃ」となった。 「無為な様」は「人にはできない様」となり、「すごいこと」へと発展したようだ。 ようやくその辺りまで分かってきた。 なお「わやくちゃ」「はちゃめちゃ」「しっちゃかめっちゃか」も、元を辿れば同じく「無茶」「無作」に由来する言葉だろう。 地方によっては「はっちゃかめっちゃか」「ひっちゃかめっちゃか」と言う所もあるそうだ。 ちなみにパラリンピックで話題になった「ボッチャ」はイタリア語で「ボール」という意味らしいので何の関係もない。 「スパゲッティ」もイタリア語で「ひも」という意味だ。 彼の地は彼の地で、もうちょっと捻れよとは思う。 [一日三報] [読売新聞] 指示役が「書類審査」と称して犯罪歴尋ね、通信アプリで犯行計画書を共有…「闇バイト」の実態
悪の秘密結社とは、たぶん黒服も着ておらず、地下に要塞も構えていないだろうが、現実にはこんな形で存在するらしい。 仮面ライダーの悪役はともかく、その下の戦闘員たちがどうして悪の秘密結社で働いているのかというと、きっとこんな境遇なんだろう。 [ITmedia] ゴキブリの頑丈さとスピード、チーターの俊敏さを兼ね備えた昆虫ロボット
嫌な予感がしてならないのだが。 より性能を高めて自己繁殖能力も備えたロボットが、世界各地の災害地へ派遣されて、そのまま定住して外来ロボット問題に発展する未来がやって来るのでは。 [テレ朝] 中国「ボーイズラブ」などを不良文化として排除要請
彼の国、彼の党の基本方針は非常に分かりやすく、要するに国家の利益に繋がらないものは一切排除するという考えだ。 国民より国家。 個人の人権は存在しない、という訳にもいかないが、それよりも国家の利益が優先される。 万事その発想で運営されていると考えれば、日本やアメリカよりも分かりやすいシステムとも言えそうだ。 それって実は、ツイッターのアイコンに日の丸を付けている右寄りの人たちと非常に似通った理念なのだが、あまり追求すると叱られそうなので黙っておく。 [今日の独言(ひとこと)]
先週の平日にユニバーサルスタジオジャパンへと行ってきた。
緊急事態宣言の解除が発表されて、入場制限の緩和が予想されたので、このタイミングで行くしかないと思ったからだ。 お陰で来場者も5000人+アルファだったので非常に快適に過ごせた。 私は妙にUSJと縁があるようで、これまでに何度となく足を運んでいる。 昨年はさすがに行かなかったが、一昨年は確か来場しており、今年で20周年らしいが、私も20回は訪れているだろう。 もう忘れられているだろうが、一時は経営が危ぶまれるほど低迷していた。 その時は園内もガラガラでアトラクションも乗り放題でとても楽しかった。 そんなUSJを長年横目で見続けてきた私だが、昔と比べて大きく変わったところがある。 それはアトラクションには力を入れずに、そこに至るまでの演出にこだわったことだ。 例を上げると、今は「鬼滅の刃」のアトラクションが人気で、平日でも160分待ちとなっていたが、少し前までは同じ場所で「進撃の巨人」か「ワンピース」が展開されていた。 ただし建物や乗り物は何も変わっていない。 周囲の壁や流れているBGM、スタッフの服装やアトラクションの映像を差し替えて、限定グッズを販売しているだけだ。 アトラクションも映像中心の室内コースターなので、絵を変えているだけに過ぎない。 だから何度乗っても動きは何も変わらない。ギューンと来てババーンとなってジャーンと終わる。 隣にリヴァイ兵長がいるか煉獄さんがいるかの違いだけなのだ。 これはコスト削減ではなく、アトラクションにこれ以上の過激化は不要と判断したからだろう。 もちろん普通のジェットコースターもあるが、それもほとんど進化はしていなかった。 私はこれを「遊園地のプロレス化」と呼んでいる。 プロレスも力道山の創設以来、肉体の頑丈さと技の過激化を追求し、より高度でダメージの大きなものが次々と開発されていった。 しかし2000年代になるとそれもファンから飽きられるようになり、一方で危険な技により選手の怪我が絶えなくなった。 特にリング禍と呼ばれる頸椎の損傷により半身・全身不随に陥ったり、最悪死亡する選手まで現れた。 そこでアメリカではWWE、日本では新日本プロレスなどが大きく方針を転換し、過激な技を控えて背景と演出に注力するようになった。 選手同士の遺恨や戦う理由をドラマチックに演出し、リングへ上がるまでのストーリーにこだわった。 試合も危険さではなく派手さを目立たせたものとなり、実は技自体は平凡だが大いに盛り上がる風に仕立て上げた。 その結果、人気は大きく回復し、安心して過激さを楽しめるショーとなった。 奇しくもジャイアント馬場が提言していた「明るく楽しく激しいプロレス」が思わぬところで実現したのだ。 遊園地も結局のところ、遊具の過激さを追い求めていては頭打ちになってしまう。 バンジージャンプのロープを足に巻くか首に巻くかを売りにしていてはブームはすぐに過ぎ去ってしまうだろう。 昨今の安全基準、心理的安心感からも外れてしまう。 たった一度の事故で閉園しかねないリスクを取る訳にはいかないのだ。 ということで、アトラクションはそこそこにしておいて、背景と演出にこだわって客を呼び込むようになった。 ある意味、当然ながらも画期的な手法だと思った。 この「○○のプロレス化」というのは他のコンテンツでも有効な手段かもしれない。 それはともかく、USJは何度行っても楽しいのでお薦めです。 [一日三報] [南日本新聞] 「ひどい頭痛持ち」が多い県 3位山梨、2位鳥取、1位は…
一位は鹿児島県とのこと。 ただしこれは頭痛を数値化したものではなくアンケートの結果なので、実際のところは何とも言えない。 私もひどい頭痛持ちなので分かるが、出血もなければ骨折でもないだけに、この辛さは他人にはなかなか分かってもらえない。 お陰で普段とのギャップをアピールするために、頭痛のない日は明るく笑顔で真面目に働くようになった。 そんなことをしているから、また頭痛が起こるのだけど。 [AFP] 900万円持ち逃げは「アート」 デンマーク芸術家が主張
私が現代アートとやらを嫌う理由は、こういうところだと思う。 壁の落書きに値段を付けたり、テクニックよりも上辺の新奇さだけを求めたり。 良いねえ、良いよねぇと身内だけでムホムホと褒めあっている様子が、ひどく薄気味悪いのだ。 [ITmedia] ファスト映画だけでは終わらないファスト問題
コンテンツが多すぎて、娯楽を楽しむよりも「楽しんだ」という経験だけを求めるようになったからだと思う。 「話題の作品を視聴した」という自己肯定感と、「話題の作品を視聴したよ」とアピールして承認欲求を満たすのが目的なのかもしれない。 しかしまぁ、それで楽しめる人がいるなら、それはそれで良いんじゃないかなとも思ったり。 著作権の侵害は問題外として。 本をファストしたいなら、表紙と裏面のあらすじだけ読めば充分じゃないかと。 |
|
|
|
||