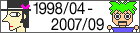|
|
||
| archive
|
[今日の独言(ひとこと)] 【ご利益ガチャ】
八咫烏(やたがらす)は熊野本宮大社に祀られている三本足の大きなカラスで神の使いとされている。
「咫」は親指と人差し指を広げた大きさ、あるいは親指と中指を広げた大きさと諸説あるが、いずれにせよ「八咫」は大きくて広いという意味がある。 日本神話では太陽の化身として天照大神や素盞鳴尊(すさのおのみこと)に使わされ、神武天皇を大和国へと道案内したらしい。 なお三本足のカラスは中国で出土した紀元前5000年の遺品にも描かれており、彼の国では金色であるとして「金烏」と呼ばれている。 そんな知る人ぞ知る存在であった八咫烏も今では日本サッカー界の象徴的なデザインとして大きく知名度を上げた。 その由来は日本に初めて近代サッカーを紹介した中村覚之助が熊野本宮大社にほど近い那智勝浦町の出身であったことや、足を使うサッカーにおいての三本足、日本を象徴する太陽の化身、ボールをゴールに導く道案内としての役割などの縁起を担いで選ばれた。 お陰で熊野本宮大社もサッカーの神社として日本代表の関係者が試合前にはお参りに訪れるそうだ。 同じようにサッカーにまつわる神社は全国に数多くあり、その多くは勝負事や足腰にまつわるものからほぼ自然発生しているらしい。 たぶんサッカーのつもりで足腰に効くとは言っていなかっただろうに、人々のなんとなくの気分で人気が生まれるというのも面白いものだ。 他にも世間には弁財天を祀っているから芸能のご利益があるとか、勉強家の菅原道真を祀っているから受験のご利益があるとか、恋愛の逸話があるから良縁のご利益があるとか、目に効く、耳に効く、頭に効く、果ては名前に金や銭が付いているからお金持ちになるといったご利益の神社もある。 特に商売繁盛の戎神社は、そのご利益にあやかろうと寄進する商売人たちによって大儲けするので、それがまた商売繁盛の証明として人を集めるというスパイラルが起きているのが興味深い現象だ。 神社にとってはいきなり何が持て囃されるかも分からない「ご利益ガチャ」の面もある。 ただ人々にとってはいつも見守ってくださっている神様よりも、これに効く、あれに効くと明確なご利益を示されていたほうが分かりやすくて参りやすい傾向にあるようだ。 まるで政治家の公約のようにワンイシュー、手広くよりも一点突破が今は受けるのかもしれない。 自分が神社を作るとしたら、何をご利益に据えるだろうか。 ただし当たるも八卦、は神道ではなく易経の教えだ。 [一日三報] [FNN] 「昭和に生まれて本当の暴走族になりたかった」“誕生日暴走”少年15人検挙
今日の昭和。 現代のサムライ的なものだろうか。 どちらも過剰に美化されすぎて、後世に受け継がれている気がする。 私が知る限り、昭和の暴走族もそんなに良いものでもなかったと思う。 そして皆が憧れるサムライや大和魂も、大抵は旧日本軍の精神性だと思う。 [毎日新聞] 「誰にも言わんどって」方言を使った特殊詐欺、急増 対策も方言
かつて薩摩の方言はあまりにも難解なため戦時の暗号にも使われたことがあるとか。 ちなみに関西弁も地方によって口振りは多岐多様に分かれており、容易には習得できないものだと思う。 「エセ関西弁」という言葉もあるが、実は地元の人間もみんな微妙に異なるエセ関西弁を話しており、総じて関西弁が作られている。 方言というのはそういうものだ。 [ITmedia]「gmail」ドメインを「gmai」と誤記、10カ月気付かず2000件超の情報漏えいか 埼玉大が「ドッペルゲンガー・ドメイン」の毒牙に
今日のネットあるある。 お陰で環境によってはサジェスト機能なので間違えないようにサポートしてくれるものもある。 でもこの記事の状況における一番の問題は、そんな機密情報を外部アドレスに自動転送させていることではないかと。 それが10カ月気づかなかったということは、いらなかったんじゃないかと。 [今日の独言(ひとこと)] 【タイマン信仰】
「タイマン」という言葉がある。
本当はないが俗語としてある。 いわゆる不良用語で、縁のあるもの同士が一対一で決闘することだ。 由来は「いったいいち」や「マンツーマン」の変形であると推測される。 ネットで調べると『古代中国でお互いが相手に腹を立てることを「対懣」(たいまん)と言っていたことが語源』とまことしやかに書かれているが、『魁!!男塾』の民明書房よろしくそんな事実はない。 本当に、ソース元が明らかでない回答はTPOをわきまえないと悪になり得ると思うYahoo!知恵袋。 先日15日、神奈川県の平塚署は恐喝の疑いで、市内に住む高校2年の女子生徒と中学3年の男子生徒を逮捕した。 逮捕容疑は8月に市内の河川敷に高校1年の男子生徒を呼び出して「金を払うか男3人とタイマン張るか選べ」と要求。 現金3万円を脅し取った、としている。 先日18日には大阪府の天満署が決闘の容疑で北新地のガールズバーの責任者の男を逮捕した。 容疑は運営する店舗での情勢従業員のトラブルの際、「お前らタイマンしたらええやんけ。場所用意したるわ」と伝えて決闘を計画。 系列の店舗内で女性2人に殴り合いをさせたとしている。 ということで一部の世界では今もタイマンが問題解決手段のひとつとして取り入れられている。 しかもそこには正々堂々、公平、誠実という認識があり、その先には分かり合えるという幻想も抱いているようだ。 私としては身体能力の差が如実に表れるタイマンほど不公平で不誠実な解決方法もないと思う。 おまけに根に持つタイプなので、やられて分かり合えるのは考えられない。 たぶんそういう人はお呼びでないのだろう。 ちなみにタイマンはステゴロ(素手同士)が前提とされているようだが、中世の決闘ではもちろん剣や刀が使用され、やがてピストルへと移行した。どうせならピストルの撃ち合いのほうが潔さそうだが、そうでもないようだ。 独特の文化として興味深いタイマン。 なお法律の「決闘罪ニ関スル件」では参加者、立会人、場所の提供者の全てが処罰の対象となる。 よし、関わらないでおこう。 [一日三報] [毎日新聞] 警察官「撃つぞ」 イノシシ、拳銃向けられ退散 名古屋
この記事を読んで「動物相手でも発砲のルールを守る馬鹿な警察官」と見るか「イノシシ相手であっても銃口を向けるとはけしからん警察官」と見るか「気迫があれば動物にも意思が伝わるのか」と見るか。 読み手の性格と主義と知識によって印象が変わる秀逸な記事だと思った。 私はすさんだ世の中のほのぼのニュースに見えました。 [産経新聞] 中国で四つんばい現象が話題 コロナ長期化でストレスか
orzってAAも最近見なくなったね。 彼の国の人はアジアンな私たちによく似ているが、性格や行動って国家や社会にかなり影響を受けるものだと感じている。 日本社会は閉鎖的な村社会と揶揄されることもあるが、十何億の人が物理的に閉鎖されている社会も、それはそれで変わったコミュニケーションが発達していると思う。 [読売新聞]「ドラゴンボール第1話掲載」と偽物の少年ジャンプを18万円で販売…読者はがきまで再現
持っていたような、持っていなかったような。 いずれにしても捨てて手元にないわけで。 古い雑誌を丸ごと完全再現するなんて、なかなか大した技術だと思うが、やっぱり本物と偽って売ったのはいけなかったか。 それはそれとして、こんな物、買ってでも欲しいのかと……欲しいのかな。 [今日の独言(ひとこと)] 【イボを集める王様たち】
今年の6月に静岡県の日本平動物園に展示されていたシロサイのツノが何者かに盗まれるという事件があった。
その後、続報を聞いていないので恐らくまだ事件は解決していないようだ。 ツノは動物園で飼育されていたシロサイが亡くなった際に採取されたもので大きさはおよそ50センチ、重さは5キロほどの立派なものだった。 なお展示場所は防犯カメラも設置されていない人目に付きにくい場所だったそうだ。 サイのツノと聞いてピンと来る人もいると思うが、「犀角」(さいかく)は漢方の高級な原料になっている。 富裕層の増えたアジアでは近年高額で取引されており、サイが住むアフリカでは密猟による絶滅も危惧されているようだ。 なおサイが絶滅へ向かう要因は密猟だけでなく地域の開発も大きい。 なんにせよ多くの動物と同じように人間の活動により個体数を減らしているようだ。 ちなみに「犀角」は昔の日本でも解熱剤としてよく用いられており、象牙と同じく世界一の輸入国になっていた。 その成分は大半がタンパク質のケラチンで、象牙は骨質だが犀角は角質だ。 つまりこれは髪や爪よりもイボに近い。 人間のイボは取り除かれて捨てられるが、サイのイボは密猟されて高額で取引されるから不思議なものだ。 もちろん薬効成分は一切ないだろう。 サイの世界ではあまりにツノが取られすぎた結果、ツノの短いサイが増えているという。 密猟を逃れたツノの短いサイが優先的に交配を繰り返すことになるからだそうだ。 これだけ科学技術が発達していながら動物のイボを買い求めるのはどういう心境だろう。 ドラクエのメダル王の心境だろうか。 いや、それだけ需要があるなら多額の投資をしてサイの頭数を増やして一大犀角市場を作れば良いと思うのだが、そういう訳にはいかないものなのか。 私は時々、自分が宇宙人になったような気分がする。 多分サイや他の野生動物たちも人間の行動には全く理解できないことだろう。 [一日三報] [読売新聞] ミサイル上空通過の後、青森で核シェルターに注目集まる…販売会社がモデルシェルターも設置
アメリカの小説や映画を観ていると、一般家庭でも当たり前のように地下室やシェルターが登場する。 かつての冷戦時代に避難所やシェルターを求める人が大勢いたからのようだ。 お陰でその秘密部屋を舞台にしたドラマも作られるようになり、エンターテイメントの幅が広がった。 いつかは東北の一般家庭にある地下室が違和感なく描かれるようになるかもしれないが、まあ無ければないほうがいいよねやっぱり。 [Gigazine] ネット上の集団行動は鳥の群れに驚くほど似ている
だからツイッターのアイコンは鳥なのか、は偶然だろうけど。 たしかイワシなどの回遊魚でも似たようなアルゴリズムが見えるとか。 これをうまく解析できれば世論を誘導し捕まえることもできるのかもしれないが、そううまくもいかないようで。 集団行動が苦手な私には使いこなせそうにありません。 [AFP] NZ鳥コンテスト、イワサザイが優勝 カカポ外しで物議も
今日の鳥。 私は全く知らない業界だが、こういうところにも物議を醸す素材だったり、流行すたりがあるようで。 やっぱり撮影者は近年の傾向を学んで対策を練って臨むものなのか。 今日び、その写真で賞は取れねーよとか、鉄道写真コンテストとかにもありそう。 [今日の独言(ひとこと)] 【CG相手にプロレスはできるか】
先日死去したアントニオ猪木は、かつてホウキが相手でもプロレスができると言われていた。
いや、リック・フレアーのコメントだったか、クラッシャー・バンバン・ビガロだったか。 プロレスは対戦相手との掛け合いによって作られる舞台芸術であるが、三者はそれを一人でもこなすことができる。 下手な相手でも会場を盛り上げて、相手を持ち上げて、自分を目立たせることができる。 つまり、プロレスがうまい、という意味だ。 優れたヒール(悪役)レスラーにもその傾向がある。 その場合は自分の残虐性をアピールして、相手の活躍を後押しして、きっちり負けることができるということだ。 近頃の映画界は、特にエンターテイメント系の作品の多くではCGの発展が目覚ましい。 マーベル系のヒーロー物だけでなく、アクションシーンでは本物と見分けが付かない背景や動きが作り込めるようになってきた。 少し前だと、たとえば「アイアンマン」ではトニー・スタークの顔以外はCGで処理されていたが、今ではシーンによっては顔も含めて全てCGとなっている場合もあるらしい。 それを見ながら俳優が声を入れているとなると、もはやアニメーションの世界だ。 製作現場がそのような状況になると、俳優が演技をする状況も変わってくる。 切り抜き処理のできるグリーンバックに囲まれた舞台で、見えないシーンと相手を前に演技をすることになるのだ。 まさしくホウキを相手にプロレスをしているようなものだろう。 果たしてそれは楽しい仕事なのか、俳優としてのやり甲斐はあるのか。 しかし考えてみれば映画俳優の原点、舞台俳優の基礎は声と動きで世界観を作り出す演技にある。 優れた舞台役者は椅子ひとつで物語を描き、コントは安っぽい書き割りで状況を生み出し、落語家は話芸のみで落ちまで付けて笑わせる。 グリーンバックで激しい戦闘シーンを一人で演じるのは俳優の本分のようにも思えてきた。 小説も文字だけで物語を紡いでいる。 何気に読んでいたが、よく考えたら無茶なことをしていると思う。 [一日三報] [NHK] 皆既月食×天王星食 時間は?方角は?今夜442年ぶりの天体ショー
今日の天体ショー。 みんながSNSに投稿しようとスマホのカメラで撮影して、その出来映えにガッカリする日。 前回は442年前、タイムトラベルで有名な信長が野望を見せていた天正の8年。 記事には信長や秀吉も見て驚いたのではと語っているが、当時は秀吉は播磨の方で兵糧攻めをしていたり、信長は石山本願寺を焼いたりしていたのでそれどころでもなかったかも。 [産経新聞] <特報>侵入の〝突破口〟は給食提供業者か、大阪・病院サイバー攻撃1週間 完全復旧は年越しへ
予想以上に長引いている被害。 給食提供業者のサーバーから侵入された可能性が示唆されているが、なぜそれが基幹システムにまで繋がってしまうのか、仕方ないものなのか。 他記事によると電子カルテが手書きカルテに変わって昔に戻ったようだと語られているが、もう10年もすれば手書きカルテを書けない医師も出てくるかもしれない。 [ABEMA TIMES]「知ったら働かなくなる」 44億円の当選金を“着ぐるみ姿”で受け取りに 中国
金額の大きさと対応の滑稽さがアメリカ的で、ある意味今の中国を意識させる。 仲が悪いふりをしているが、結構2国は後ろ手で握手していると思う。 うっかり殺されないよう気をつけてほしい。 [今日の独言(ひとこと)] 【「どんごろし」をご存じですか?】
「どんごろし」という物を知っているだろうか。
前に「ミナゴロシ」という小説を書いた私も、つい最近まで知らなかった。 とある農家の手伝いに行った際、ぬかるみにはまった軽トラックを引き上げるには、タイヤの下にどんごろしを敷けば良いと教わった。 どんごろしがタイヤに絡んでタイヤの空滑りを抑えてくれるのだ。 どんごろしは大体どこの納屋にもあるので使い勝手が良いそうだ。 農業、土木業、あるいは釣りやキャンプが好きな人なら知っているだろう。 「どんごろし」とは目の粗い麻の袋のことだ。 一番見覚えがありそうな物としては、ブラジルなどから送られてくるコーヒー豆の入った袋だろう。 喫茶店のディスプレイなどでも見かける、業者の刻印がされた大きな茶色い袋、あれのことだ。 俗名だが正確には「ドンゴロス」と呼ばれている。 ネットで検索すればアマゾンのショップでも売られている共通語だ。 英語では「ダンガリー」となるが、実は語源はヒンディー語だ。 また日本では「南京袋」とも呼ばれている。 海外から来た麻の袋という意味で伝わっているのだろう。 私の周辺では「ドンゴロス」は「どんごろし」と呼ばれている。 それは口頭による呼び名の曖昧さではなく、恐らく呼びやすさと語感の面白さから誰かが言い出したのだろう。 それこそ「皆殺し」「半殺し」「半ざらし」「切り干し」「開けっ放し」「ろくでなし」「知ってるし」「やってるし」「安し」「うまし」と、日本語は「~し」で終わる言葉も多い。 「ドンゴロス」と呼べばよそよそしいが、「どんごろし」と呼べば身近な感じもするだろう。 ちなみにどんごろしは大きくて強くて丈夫で長持ちするので、様々な用途で重宝されている。 それだけに納屋にあったのも新品ではなく、明らかに海外から来たコーヒー豆の袋だった。 一体どういう経緯でやって来たのか、下取りされたものがJAで売られているのか私は知らない。 どんごろし、どこから来たのか、誰が作った物なのか、遡っていくとまた面白い発見があるかもしれない。 [一日三報] [読売新聞]「バイク」「たばこ」「軽乗用車」たどり捜査9年…「王将」社長射殺、組員逮捕へ
社会派ミステリー的な捜査展開。 ドラマや小説ならあっさりとアシを辿れてしまうところだが、実際には9年もかかる地道な捜査だった。 それでもちゃんと容疑者に結びつけられたから良かったが、時間と労力を掛けても解決できなかった事件も多いことだろう。 逮捕状が取れた時はガッツポーズが出たかもしれない。 [読売新聞] 出勤途中に「蒸しパン」食べたバス運転手、乗務前にアルコール分が検知…市「厳しく対応」
実は今年の10月から社用車を持つ事業者におけるアルコール検知器を用いた酒気帯び確認が義務化される予定だった。 実際には直前になって延期されたが、すでに対応している企業も多いらしい。 そのお陰で検知器メーカーは大儲け……かどうかはともかく、バスもタクシーもトラックも、それどころか一般の営業車を運転する人も乗る前にアルコールチェックが必須になった。 ということで、今後はこういうニュースをよく目にすることになると思う。 [AFP]「世界一汚い男性」死去、94歳 イラン
絶対に近づきたくはないが、なぜ今さらになって村民が風呂に入れてしまったのか疑問。 風呂は案外と体力を使うので老人には気をつけなければいけない。 老人は生活の習慣が変わると凄くストレスになるので気をつけなければならない。 藤子・F・不二雄の「コロリころげた木の根っ子」よろしく、計画的な犯行だったのかも。 |
|
| |
||