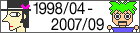|
|
||
| archive
|
[今日の独言(ひとこと)] 【現代社会における探偵の価値】
2020年のロックダウン中に、オランダ・アムステルダムのフローニンゲン美術館から盗まれたゴッホの絵画が、このたび無事に発見されたらしい。
ちなみにオランダ語で「○○ニンゲン」は「○○の土地・居住地」、転じて「村」の意味になるため地名によく使われている。 有名な「スケベニンゲン」もオランダの地名だ。 それはともかく、先のゴッホの絵画は先に窃盗犯は捕まっていたが、絵画そのものは他の場所へと移されていた。 それをアルトゥル・ブランドなる著名な美術探偵が、何かしらの手段で手に入れて美術館へ返却された。 なお絵画の価値は最大で9億4000万円とされるそうだ。 法律と科学と組織の発展により、近代警察の捜査はもはや個人の及ぶところではなくなった。 シャーロック・ホームズや明智小五郎が活躍できる場はなく、当然ながら警察が仕事を依頼したり、出し抜かれて臍を噛むようなこともないだろう。 ただ一方で警察捜査にも難しい点があり、ひとつの事件に対応できる捜査員と期間が限られている。 日々発生する事件を効率よく、適切に処理するためには仕方がない。 社会的影響の大きい事件ならまだしも、何十人もの捜査員が何年も、あるいは何十年もかけて同じ事件にあたっている余裕はないのだ。 探偵はその点、依頼者の希望と予算よっていくらでも捜査を続けることができる。 資産家が望むなら、探偵が何十人もの捜査員を雇って飼い犬を捜索することもできるだろう。 また警察が入り込めないコネや裏ルートを用いて専門的な捜査活動を行うこともできる。 先の美術探偵は「機密保持と引き換えに作品を返却する」という申し出を受けて、とある人物から盗まれた絵を取り戻したという。 恐らく警察や美術館へ直接返却できない理由があったのだろう。 どこでどれだけの人や金が動いたのかも明かされない。 国内外にかかわらず、そういう闇は割と身近に、確実に存在するようだ。 ということで、専門性に特化すれば未だ探偵が生き残る場所は残されており、つまりは創作にも活かせるかもしれないと思った。 [一日三報] [ロイター] 温暖化でまん延加速、蚊と渡り鳥が拡散する感染症の脅威
長すぎた今年の夏にもようやく終わりが見え始めている。 しかし来年はどうなのか、徐々にこの異常気象がデフォルトになりつつあるようで心配。 それでも人間は色々と対策をとって乗り切れるが、自然界では想像以上に大きな変化が起きている気がする。 まあ、それもまた自然の営みだから、という気持ちもあるが。 ただ熱帯の動植物は攻撃的な奴らが多いから怖い。 [CNN] 「グーグルマップが崩落した橋に誘導」、転落死の男性遺族がグーグル提訴
グーグルに限らず、の問題だと思う。 狭くて地元の人間も普通は通らないような道が急に混雑するようになったら、だいたいカーナビがルートに指定しているわけで。 案内されたからって崩落した橋に落ちるか? と思われそうだが、音声案内で「行けます」「行けます」と言われ続けたら信じてしまう傾向が強いと思う。 これが隣の人の主張だったら逆らえそうだが、何か信頼感に違いがあるような気がする。 [朝日新聞] 「地下鉄サーフィン」、NYで若者の死亡相次ぐ 動画拡散の影響も
パルクールの発展型みたいなものだろうか。 積極的に死のうとするアホを止めるのは難しい。 人は痩せると言われたら毒でも飲み干し、クールと言われたら走っている電車にも飛び込む。 それでいて、いきなり何の理由もなく急に「危ないし、格好悪いよ」と素に戻って一斉に止める。 バブル期のテレビ映像を見て、みんな肩幅広すぎだろって思うように。 ああいう情動の変化って何だろうな。 [今日の独言(ひとこと)] 【未知の生物、その名はワニ】
メキシコ議会は先日12日、公聴会で「人類ではない」生物の遺体を2体が公開した。
ジャーナリストのハイメ・マウサン氏が2017年にペルーで発見したとするもので、灰色がかった小さな人類のような体形をしている。 「正体が分からないので、地球外生命体とは呼びたくない」として、炭素年代測定から約1000年前のものであると証明されていると語った。 事実とすれば驚くべき発見だが、公開されたその姿はグレイとETの贋物のような、なんともステレオタイプな見た目をしている。 なおマウサン氏は数年前にもエイリアンのミイラと称して人間の2歳児の遺体を公開したこともあるようだ。 未知なるものや未確認生物に興味を抱くのは人類共通の性質か。 先日、三重県尾鷲市の学芸員が市所蔵の古文書を調べていたところ、江戸時代に「ワニを探して欲しい」という通達があったことを発見した。 明和7年(1770年)に税金を徴収する機関から地元の役人に「わにと申す魚」を探し、「見つけたら塩漬けにして送ってほしい」と書かれていた。 古来、日本では近海に住むサメのことをワニと称していたことはあるが、同書には「形はイモリに似て」「腹は蛇腹」「四足で足には四本の爪がある」と書かれており、明らかにサメではなくワニそのものを示している。 なお回答には「漁師たちも見たことがない」と書かれていたそうだ。 一体どうして役所が、しかも税金を取り扱う機関がワニを探し求めていたのか。 事情は定かではないが、あるいは「お殿様がご所望」だったのかもしれない。 明和7年の紀州藩の藩主は徳川重倫(しげのり)という人物だが、この人は傍若無人の乱暴者と知られている。 気に入らなければ家臣を斬り捨て、江戸屋敷では隣の松江藩の婦女を銃で撃ち、なぜか庭に豆腐を積上げさせては、集まってきたカラスを撃つという謎の遊びも行っていた。 まさに暴れるだけの暴れん坊将軍という人で、そのため幕府も捨て置けず30歳で隠居を言い渡されたようだ。 こんな人物なら、ワニという珍しい動物の話を聞いて探させたというのもありえる話ではないだろうか。 ちなみに先の文書では「見たことがない」という記述のあとに「見つけたら、すべてを投げ出してでも逃げ去るため、姿を完全に見た者はいない」とも書かれているらしい。 なんとなく、暴君の機嫌を取るための言い訳にも思えた。 ちなみに息子の徳川治宝(はるとみ)は御三家当主で唯一、生前に従一位に叙せられた名君と知られている。 ワニ騒動の翌年に誕生しているので関係はない、と思うが。 [一日三報] [AFP] 「つながる車」、個人情報だだ漏れの恐れ 調査報告
今日のIoT。 車も冷蔵庫も腕時計もランニングシューズも、なんでもかんでも繋がりたがりの世の中。 別にユーザーはそこまでの繋がりを求めていないと思うが、繋がってシェアをすることが人類の新たな行動原理となってしまったので、利用しないわけにもいかないわけで。 その辺の感覚はもう諦めたけど、勝手に繋がってはしょっちゅう流出だのエラーだのを起こして煩わせるのは、ちょっとどうかと思ったり。 [ITmedia] 犬と同居している人はiPhone、猫と同居している人はAndroidのユーザーが多い傾向に ドコモ調べ
面白い調査だと思うけど、結局ここでは語られていない「収入の差」も大きいように思う。 みんなタダで配られたわけじゃないし、犬と猫とじゃそもそもかかる金額も違うし、犬と猫の両方を飼っている人がアクティブというのもそうだと思う。 一方で、犬を飼いそうな人ほど、犬を飼える環境を得やすいという側面もあるかもしれない。 「犬とインコ」とか「犬とカブトムシ」くらいなら、より性格の差が出るような気がする。 [CNN] 「集団殺人儀式」の通報で警察急行、実はヨガ教室 英
今日のマハーポーシャ。 ヨガといえばインドのリラクゼーションなアクティビティだが、おじさん世代にはアメリカ人はヒッピーに走り、日本人は修行に走ったイメージが強すぎて、なかなか受け入れられにくい面もあると思う。 というか、今でもヨガを利用したアレ系団体もいくつか活動しているわけで。 やっぱりこう、暗がりでエネルギーを得るスピリチュアルな活動は親和性が高いのか。 でも悪いことをしなければ個人の勝手で良いと思う。 [今日の独言(ひとこと)] 【紙代が高騰すると電子書籍も高くなるよ】
北海道新聞の夕刊が九月末で休刊になるらしい。
理由は原材料費の高騰や輸送コストの上昇とあり、要するに紙代とガソリン代が上がっているということだ。 ちなみに同刊は1992年のおよそ78万部をピークに現在は23万部と、およそ30年で3分の1にまで落ち込んでいるそうだ。 新聞といえば日刊紙の大阪日日新聞も7月末で休刊となっている。 こちらも同じく資材費や流通費、配送費の高騰を理由にあげていた。 私はもう紙の新聞からは卒業したので、これらの新聞も購読していない。 ただ原材料費と輸送コストの高騰は新聞のみならず、出版業界全体の大きな懸念となっているようだ。 ユーザーのニーズや生活スタイルの変化もあって長らく出版不況と言われているが、今は製作コストの上昇も大きな理由となりつつある。 良質の紙とインクを使ったグラビア誌なども影響は大きいだろう。 製作コストが上がると小説が出版されなくなるかというと、そういうわけではない。 ただし、ページ数や部数の管理はよりシビアになってくるだろう。 そして書籍の価格に反映されるようにもなる。 文庫本の価格はここ30年で6割も上昇し、一冊千円を超える作品も見かけるようになってきた。 文庫本といえば高い新書のハードカバー本に対する廉価版という扱いだったはずだが、今は初版から文庫本である場合も多い。 それがこれだけ高価なると、購読を渋るユーザーはますます増えていくことだろう。 また紙の文庫本が値上げすると、電子書籍も値上げになるのは必然だ。 電子書籍は紙やガソリンを使わないが、特に新刊の場合は紙の書籍と価格を近づけるのが業界では普通だからだ。 そうしないと不公平が起きて紙の書籍が売れなくなってしまう。 紙の書籍が売れないと書店も取次業者も印刷所も困ってしまう。 そうなると出版社も著者も困ることになる。 端から見ればおかしな話かもしれないが、そういうものなのだ。 紙書籍の出版が今後どうなっていくかは分からないが、そのうち大転換が起きると思う。 それは今の音楽配信とCD販売に近いもので、日常的に消費される電子書籍と熱心なファンやコレクターが求める紙書籍という扱いになるだろう。 すると出版の形態も変わり、電子書籍のみの出版が増えて人気が出れば文庫化するという形になるかもしれない。 漫画雑誌がやっている、新人をピックアップしたWEB配信のようなものだ。 小説界も今後はそういう流れが起こるのではないだろうか。 [一日三報] [中央日報] 「自分がサイコパスなのか気になった」20代のブラジル人女性、友達を殺害
一部の研究によると大企業の経営者や国家のリーダーにはサイコパスが多く、また株主や国民もサイコパスを求める傾向にあるという。 サイコパスとは反社会性パーソナリティ障害という一個性に過ぎないが、メディアやエンタメの影響で「猟奇的殺人者」というイメージが強い。 そのせいでサイコパスだから危ない、他人に冷たい自分はサイコパスかも知れないという思い込みが横行しているのではないだろうか。 私からすれば、大体みんな一部分ではサイコパスだと思う。 [CNN] ブルーライトカットのめがね、目の負担軽減の助けにならず 国際研究で結論
そんなことないだろうなと思っていたら、やっぱりそんなことなかった。 ブルーライトカットとブルーベリーは目に効いているような気もしないわけで。 とはいえ昔のCRTモニタに対してはどうだったのか、目がかすむほどの栄養不足の人に対してはどうなのか。 でもなんか、「ハゲに効く!」的な、弱みに付け込んだ誇大広告じゃないかと思う。 [朝日新聞] 「せんとくん」以来の新キャラ起用 奈良県がVチューバーの県民投票
今日の奈良。 県民の感覚としてこう、いつも取り組みが2、3テンポ遅れているというか、石橋を叩いて壊しているような気がする。 3人いるなら3人にやらせればいいのに、なぜ1人を選ぼうとするのかな。 あと「せんとくん」が最終的に大成功みたいな扱いを受けているのは、デザインセンスの敗北でもあると思う。 [今日の独言(ひとこと)] 【覚えられない題名、忘れられない題名】
福井県立図書館のサイトにある「覚え違いタイトル集」のページを時々見ている。
福井県立図書館 | 覚え違いタイトル集 以前にも紹介した気がするが、図書館の利用者が司書に確認した際、誤って記憶していた書籍のタイトルを紹介している。 『100万回生き返ったねこ』→『100万回生きたねこ』 『老いを謹む習慣術』→『老いを愉しむ習慣術』 『茄子(なす)の花』→『芥子(けし)の花』 『お手玉るいさんの本』→『小手鞠るいさんの本』 『ヤンデレBLっぽいミステリー。有栖川有栖の書いた本に似たようなミステリーがあった気がする。主人公はミノムシみたいな名前』→『孤島の鬼』 ※ちなみに主人公の名前は箕浦。 少し違いの惜しいものから、全く繋がりのないものまで、人の記憶と思い込みの曖昧さと、そこから求めている書籍を探り出す司書の力量が窺えて楽しい。 数年前にはそれらのケースを集めた『100万回死んだねこ 覚え違いタイトル集』という書籍も出版された。 書籍のタイトルというのは著者が頭を振り絞り、心血を注いで、一筆入魂の思いで付けるものだが、読む人は割と適当に覚えているものだ。 私はあまり考えずに短い方が覚えやすいかなと思って付けることが多いが、それでもちょくちょく間違えられる。 書籍のみならず色んな商品の名前もそうだろう。 でもそれっぽい名前でも大体通用する優しい世界なのは、デジタル社会との差かも知れない。 一方で、意味の分からないタイトルながら、なぜか記憶に残って覚え続けているものもある。 私の場合だとすっと思い出せるのは『ディプロトドンティア・マクロプス』。 我孫子武丸の作品で、カンガルーを見つけて欲しいという依頼から訳の分からない方向へと進んでいくユーモアミステリ小説だった。 もう一つは『ディエンビエンフー』。 西島大介のマンガでベトナム戦争を舞台に少女が殺戮を繰り返す、可愛さとリアルが詰まった作品だ。 ディエンビエンフーはベトナムの地名でそのまま『ディエンビエンフーの戦い』という戦争で有名だが、私は知らなかったがお陰で完全に記憶できた。 もしかすると『ディ』で始まる言葉が印象に残るのか。 あと一つ思い出せるのは『イワーン・イワーノウィッチとイワーン・ニキーフォロウィッチとが喧嘩をした話』 ロシアの古典作家ゴーゴリの作品で、なんとイワーン・イワーノウィッチとイワーン・ニキーフォロウィッチとが喧嘩をする話だ。 ちなみにゴーゴリはロシア帝国領であった現在のウクライナの出身で、少し前の生誕200周年には氏の『所有権』を巡ってウクライナとロシアが言い争いをしていた。 ということで、名称は適当に覚えていてもなんとかなるみたいね。 [一日三報] [ITmedia] 渋谷を歩くだけで年齢から行動、服のブランドまで筒抜け? “AIカメラ100台設置プロジェクト”が物議
今日の監視社会。 まあ渋谷はベストオブ社会都市ともいえる街なわけで、訪れる人々も自由な個より管理される構成要素の一つとして含まれる覚悟はあるべきだと思っている。 徹底的な監視を受けた結果、犯罪を抑えつつ、誰にとっても便利で遊びやすい街になるとすれば、それもまた良いのではないだろうか。 問題は、大抵そんな風にはならず、余計なトラブルを生む場合が多いことだが。 [AFP] 「話題を変えましょう」 ウイグルや台湾について百度の対話型AIに質問
これは彼の国での話だが、別の国にせよ、別のAIにせよ、行き着く先はこんな使い方になると思う。 みんなで力を合わせたら幸せになれるという、集合知や性善説は、結局のところインターネット社会を見れば幻想に過ぎなかったことが分かったわけで。 せっかくのAIの知もエライ人たちによって都合良く歪められていくと思う。 AIが反論できない根拠をもって決定した「悪」を、我々は否定できるだろうか。 [CNN] 隕石から作られた3000年前の矢じり、スイスの湖近くで見つかる
流星刀か、弓と矢か。 『ジョジョの奇妙な冒険』では矢で貫かれた人がスタンド能力を発現させるが、あれも確か隕石から作った矢じりが宇宙由来の細菌か何かを含んでいるのが理由だったかと。 後付け設定だったけど。 なんにせよ隕石には未知のロマンがあるわけで、創作物だと大体最強クラスの武器に加工されるね。 そろそろ月の石や火星の石を持ち帰って、何か彫刻されるようになるかも。 |
|
| |
||