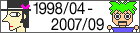|
|
||
| archive
|
[今日の独言(ひとこと)] 【インフル病みの駄文ロフ】
先週一週間、インフルエンザに罹患して倒れていた。
高熱からくる悪寒と頭痛、関節痛。 咳と鼻水と全身疲労。 前触れもなく訪れる、目には見えない外敵と戦い続けていた。 西暦737年の奈良時代、当時朝廷において権勢を振るっていた四人の兄弟が相次いで病死するという変事が起こった。 四人とは右大臣・藤原不比等の息子、藤原武智麻呂、房前、宇合、麻呂。 全員四十代から五十代の若さだった。 人々は四兄弟の死に対して、数年前に陰謀によって自殺へと追い込まれた長屋王の祟りではないかと噂した。 その後、四兄弟の死因は当時不治の病とされていた天然痘によるものと判明。 仲の良い兄弟がそれぞれ見舞いに訪れた際に感染したものと推測されている。 ウィルスも細菌も知らない時代の人たちからすれば、全身にかさぶたができて死に至るなど祟りや呪いとしか思えなかっただろう。 この事件は後に東大寺の大仏を建立するきっかけにもなった。 とはいえ、現代においても、インフルエンザにせよコロナにせよ、その正体や対策方法が分かっていても感染する人としない人がいる。 体力のある若い人でも罹患することもあれば、もう色々とギリギリなご高齢者でも全く平気なこともある。 その違いは結局のところ運のようなもので、つまりは祟りや呪いと同じではないかとも思う。 大仏は建立しなかったが、アマビエとかいう落書きを持て囃す人たちは少なくなかった。 どこから発生しただの、誰から感染しただの犯人捜しをする人たちもいる。 ワクチンが良いだの悪いだの陰謀だのと騒いでいる人たちもいる。 根本的には奈良時代の人たちとあまり変わらない気がした。 ともあれ皆様、お大事に。 [一日三報] [ITmedia] 小中学生の4割が「学校でずっとマスクを着用」、理由は?
僕らはもう大人なので、このマスク習慣が一時的なものと知っている。 その後は着けるなり外すなり好きにすればいいし、文句を言われる筋合いもない。 しかし小学生にとってみれば強制であり、厳しく指導された戒めはなかなか解くことができない。 ウィルスが飛んでいるからマスクを着けさせられたのに、まだウィルスは飛んでいるのにもう外せってどういうこと? となるだろう。 そしてインフルエンザ上がりの私としては、着けっぱなしで一生を過ごす時代としていいような気もしている。 怖いよほんと。 [CNN] アラスカ周辺のズワイガニ、数十億匹が姿消す 海水温上昇に起因と科学者ら
一攫千金といえば日本ならマグロ漁船、アメリカならベーリング海のカニ漁というイメージ。 でもこちらも昨今は気候変動の影響を受けている模様。 漁師さんたちもあまりうま味がなさそう。 カニはおいしいけどね。 [ロイター] 米33州、メタとインスタ提訴 若者のメンタルヘルス危機助長と主張
そんなに面白いか? と思うけど、いくら見続けても追いつかないコンテンツ量も問題だと思う。 日本の人もずっとプチプチ触っている人がいるわけで。 移動中や空き時間なら分かるけど、他人と話している間とか食事中までやっている人を見ると、何だか可哀想だなという気持ちにもなってくる。 それも人の勝手だろうけど、多分そこに答えはないよ。 [今日の独言(ひとこと)] 【個人サイトと前世紀エヴァンゲリオン】
気がつけばホームページを始めてから26年経っている。
1997年、19歳の時に初めてアップロードしてから45歳の現在も続けている。 その間、色んなことが起こり続けたが、書くことだけはやめなかった。 なんだか性に合っていたということだろう。 いい玩具を見つけたものだと今は思っている。 当時は個人ホームページの全盛期で、名もなき個人が大勢の目に触れるという、今のSNS時代の黎明期でもあった。 その中心となったのは、それまで日の目を避けて活動を続けてきた、というか見られる機会を与えられてこなかった、いわゆるオタクと呼ばれていた人たちだった。 そして活動のエネルギー源となっていたのは『新世紀エヴァンゲリオン』だ。 他にも色々と要因はあった、と言いたいところだが、真っ只中を横目で眺め続けてきた当事者としては確信している。 ニコニコ動画がYoutubeの動画をパクっていた時代よりもずっと前、マクロメディアのFlashやShockwaveで個人アニメやゲームが爆発的に増えるよりもさらに前、個人とメディアの間に道路を引いたのは前世紀のエヴァンゲリオンだった。 あのアニメのインターネットにおける貢献度は凄まじく大きかったと感じている。 あれから26年、社会も私も変わったようで変わっていない今を生きている。 ただもう一個人がHTMLをいじってホームページを作る時代ではなくなった。 niftyもso-netもgeocitiesもBekkoameもそんな業務を終えて、今私がサイトを運営している会社もとうの前からやる気を失っている。 そろそろ私もプラットフォームを移す頃かなと感じつつある。 ただその見極めがなかなか面倒臭いのだ。 今のところ勢いがありそうなのはアメブロかnoteだろうか。 でもアメブロはなんだかゴチャゴチャしているので、今はnoteを少し触っている。 ちょっと物静か過ぎるのは気になるが、そう悪くもなさそうなので機会を見て移転してもいいかなと考えている。 26年前ならよーし引っ越しだーと乗り換えていたが、今はぼちぼちと進めていくしかない。 いやもう面倒臭いのよね、何もかも。 息をするのも面倒臭い。 昔ホームページを運営していた人や、それをROMっていた人たちって、今どうしているんだろう。 色々あったと思うけど、みんなそれぞれの場所で幸せになっていたらいいね。 [一日三報] [大学ジャーナル] 「草」と「木」の新しい分類方法、力学理論により北海道大学が発見
要するに、内部の水分で自立しているのが草、自重で自立しているが木、という感じか。 乾燥でしんなりしたら草、カサカサだけどそのままなのが木、とも言えそう。 つまり長年の疑問だった「竹」は、これで「木」の一種であることが決まったわけだ。 次は「チョウ」と「ガ」の違いを決めて欲しい。 [理化学研究所] カマキリを操るハリガネムシ遺伝子の驚くべき由来
みんな大好きハリガネムシ。 人間の爪の間から入ったりはしないので安心してほしい。 よく分からないが、宿主のカマキリから行動に繋がる遺伝子を取って操作しているらしい。 病原体や化学物質の仕業ではないとか。 ていうか遺伝子を取るって何? [下野新聞] 雷鳴抄「ポケモンスリープ」
ここはお前のホームページか。 お手本のようなコラムだが、いまいち何だか分からない。 それは多分、記者の名前もプロフィールも伏しているからだろう。 俺が俺がのネットメディアと違い、オールドメディアの方が匿名性が高くなるのは興味深い。 [今日の独言(ひとこと)] 【相貌失認それがどうした】
コロナ禍以降、オンラインで人に会うことが多くなった。
仕事柄、奈良に住みながら東京の人と会議や打ち合わせを行うことが多いが、出張で対面することはほとんどなくなった。 そもそも一緒に野球をしている訳でもないので、顔を会わせないことで生じるデメリットは何一つない。 オンラインミーティングとデータのやり取りだけで、特にトラブルなく仕事を進めていけるのだ。 人によっては直接顔を合わせないと仕事ができない、あるいは挨拶に来ないとは何事だという大先生もいるかもしれないが、私はできることなら対面せずに済ませてしまいたい。 なぜなら私は人の顔を覚えるのが極端に苦手で、誰が誰だか分からなくなることが多いからだ。 だから駅で待ち合わせをする際も、相手から声をかけられるまで待ち続けることが多い。 会って言葉を交わしてから、ようやくこういう人だったなと思い出す。 ぶっちゃけ、外で会えば親の顔もよく分からない始末だ。 ネットによるとこれは「相貌失認」(そうぼうしつにん)という脳の症状らしく、割と自覚している人も多いらしい。 人によっては自身の怠慢や冷酷な性格のせいと思い込み、私はダメ人間だと落ち込む人もいるそうだ。 職場や仲間を大切にする、優しい人ほど苦労することだろう。 私が悪いのではなく脳の症状なのだと、周囲に理解を求めて訴えている人もいた。 一方、それに対して、警察では張り込み捜査などで、雑踏の中に紛れ込んだ犯人の顔をピタリと当てる人がいる。 それは犯人がマスクを付けてカツラを被っていても見破ることができるらしく、私からすれば魔法を使うかオーラか何かを見ているのではないかと驚くほどだ。 また宿泊業や飲食店の女将さんなどでは、何年も会っていなくても、その人の姿と経歴と当時の出来事をすっと思い出せる人がいる。 これらは相貌失認の逆と呼べる能力だろうか。 「人たらし」と呼ばれた豊臣秀吉や田中角栄などもそういう傾向があったらしい。 そういうエキスパートな人たちと比べたら、しょせん世間の人も相貌失認の気があると言える。 普通、標準、当たり前などあってないようなものだ。 私は何でもかんでも脳の症状や病気と名付けて重大に扱うのは好きではない。 人間誰しも得意、不得意はあるもので、それでも仲良くやっていくのが社会と法律だと思っている。 人の顔を覚えられない人は、隠さずに前もって相手にそう伝えておけばいい。 それで大体は認めてもらえる、というか、別にあなたが思うほど相手はあなたに興味もないだろう。 もしくは、相手に放っておかれない人になるとか。 他人の顔など覚えなくても大した問題ではない。 好意を伝える方法は他にいくらでもあるはずだ。 [一日三報] [テレ朝] 手紙を書くのが苦手でも…“思い”を文字に AIが筆跡や筆圧を再現
今日のフェイク筆跡。 問題はその綺麗な字で書く文面だと思うが、それもAIでよろしく出力してくれるようになるかも。 そう遠くない未来、私たちが生きている内にでも、文章文面の自動化が当たり前になるかもしれない。 ただ問題は、今がその過渡期にあるわけで、結局私たちは一番苦労して死ぬことになるだろう。 [ITmedia] 新鉱物「桐生石」と「群馬石」を発見 ネット上の地質図への“違和感”がきっかけに
今日のマインクラフト。 こういう研究をしている人だと、山や地面を見ても楽しめることだろう。 マイクラだと変なブロックを見つけたらテンション上がって調べに行って、スケルトンに狙撃されるけど、現実だとその区別も付かないし興味も湧かない。 なぜだろう、土だからかな。 [CNN] 臨死体験、心停止後の脳の活動と関係か 新研究
仏教とかで厳しい修行や絶食の果てに仏の姿が見えたって話があるけど、あれ絶対死にかけているだけだよね。 国籍や宗派や人種や性別にもとらわれず、臨死体験中のイメージが大体共通しているのは、それが脳の科学的反応によるものという証拠だと思う。 絶対死にたくないと思うような地獄を見た人っていないわけで、きっと死の瞬間は本当に幸せな気持ちになれるのだろう。 これは突き詰めると死にたくなるから危険な研究だ。 [今日の独言(ひとこと)] 【推しの賞味期限とは】
私は未だ「推し」という言葉に抵抗を感じる中年だが、世間ではもう一般用語として浸透しているらしい。
「推しメン」や「推し活」も一発で変換できて、「推し、燃ゆ」や「推しの子」などの創作作品も話題になった。 先日公表された文化庁による「国語に関する世論調査」でも49.8%の人が「使うことがある」と回答。同時に82.1%の人が「他人が使うことが気にならない」と回答した。 「推し」という言葉がいつどこから使われるようになったのかは知らないが、語感から推測すると、いわゆるアイドルオタクと呼ばれる人たちが集まるBBS(掲示板)界隈ではないか、あるいはそこで一般化されたように思える。 ひとつに「推し」という言葉は口答では伝えにくく、文字にして初めて意味が分かること。 もうひとつにオタクは自分たちがオタクやマニアと呼ばれることを嫌い、性癖を示す新しい言葉を求め続けていたことだ。 そうして生まれた「推し」という言葉が、趣味の分散時代におけるオタクやサブカルの一般人化にともなって、ネガティブなイメージを払拭する新しい言葉として爆発的に広まったものと思われる。 さらにその対象が人間にこだわらなくなり、単に「私が好きなもの」として「鉄道推し」や「キャンプ推し」などにも発展した。 私は言葉というのは時代を食べて成長する生き物だと考えている。 だから言葉に「正しい言葉」という乱暴なものは存在せず、「伝わる言葉」として時代とともに移り変わっていくものだ。 たった150年ほど前に書かれた江戸時代の書物はひどく読み難いが、当時の人々はすらすら読めて意味も深く感じ取っていただろう。 今私たちが読み書きしている文書も、あるいはプロが書いた名筆も、たぶん100年後の人たちが読めば訳の分からない、つまらない昔の言葉に見えるはずだ。 そして「推し」の普及によって、そろそろ「オタク」や「マニア」が死語となっていく気もしている。 代替語によって置き換えが進むとともに、人の好きな物事を貶す言葉を自粛する風潮もあるからだ。 なんだろうね、この勝手自粛、あるいはセルフ・コンプライアンス。 というか、行政や企業などの広報にとっては、ようやく暗くて重い「オタク」に代わる、ポジティブな言葉が生まれて喜んでいるだろう。 やっぱりネガティブな言葉はみんなが避けるから、いつかは廃れるのだ。 とはいえ「推し」もこじらせて心を病むケースも多い。 いつしかネガティブなイメージへと変わるか、あるいはその前に廃れていくか。 「推し」自体もまた賞味期限がある言葉だと思う。 [一日三報] [産経新聞] DX、SNS、AED…8割超「略語の意味わからず困る」 国語世論調査
大丈夫、みんな大して意味も分からず使っているから。 それはともかく、世の中には『アルファベットの略語』という時点で一切理解を拒否する人たちも一定数いることは知っておいたほうがいい。 しかもそれは高齢者ばかりでなく、割と若い人たちにもいるようだ。 まあ使いたがりのビジネスマンはともかく、みんなが使う行政や高齢者の多い場では、もう少し通用する日本語を普及させたほうがいいと思う。 [AFP] AIゴッホ、切り落としたのは「耳のほんの一部」 仏美術館展覧会に登場
こんばんは、織田信長です。 少し前に亡くなられた宗教家は死者の霊魂か何かを下ろすのが得意だったが、もう少し長生きしていればAIによって効率化が図れたかもしれない。 というかご本人をAI化して、その上で別人の降霊を行ってもらったら面白いことが起きそうだ。 それはともかく、こういう取り組みは目新しいけど誤解を生むことにも繋がりそう。 AI化された本人が語っているのだから事実だという認識が広まりそうな気がする。 [ナショナル ジオグラフィック] つらい記憶のフラッシュバックは「テトリス」をやると減る、研究
たまにお婆ちゃんとかで、他のゲームを一切やらずにずっとゲームボーイでテトリスをしている人がいる。 あれも辛い過去を忘れるための行動なのかもしれない。 人間ヒマになるとロクなことを考えないので、単純作業でもしていると気持ちが楽になることはよく言われている。 私はパチンコをやらないので何が楽しいのかさっぱり分からないが、あれも実はパチンコが楽しくてやっているわけではないのかもしれない。 当人にとってはエステとかアロマとか、そういう効果を得ているのではないだろうか。 [今日の独言(ひとこと)] 【やがて世界は巻物に戻る】
タブレットに慣れきった幼児に紙の絵本を与えたら、絵に指を置いてなぞるようにスワイプしていた。
という冗談みたいな話もあるが、今時の子供はそれほど紙の本よりデジタル画面のほうが主流となっている。 週刊少年ジャンプの発行部数は全盛期の1/3以下にまで落ち込んでいるが、それは漫画がつまらなくなったからではなく、書店へ足を運ぶことなくWEB版など、それ以外の方法で楽しむようになったからだ。 紙の書籍とデジタル書籍との大きな違いはページの概念だ。 スマホやタブレットで読むにはページをめくることなくスワイプさせる。 電子書籍ではわざわざページがペラリとめくれるアクションも付いているが、あれも紙の書籍がなくなると意図を理解できない人々が増えると思う。 「動画の巻き戻しって、何を巻いているの?」と同じように、「電子書籍って左下から何を剥がしているの?」と思われるようになりそうだ。 そもそも書籍というか紙を綴る本の概念がいつ生まれたかというと、紀元前かいつかの時代の羊皮紙にまで遡る。 それ以前に作られていたエジプトのパピルスは巻物として使われていた。 一方で羊皮紙は丈夫で両面に書くことができたので、一枚の紙を束ねて綴じた書籍として使われるようになった。 とはいえ両者は移行したのではなく、地域や使われ方で巻物も綴じ本も併用されていた。 そして15世紀にグーテンベルクか誰かが活版印刷を発展させたことで、綴じ本が主流となった。 そして現代、デジタル書籍にページの概念はなくなり、その形態と使用は巻物によく似ている。 スクロールとはそのまま「巻物」という意味だ。 これにはエジプトの書記神・トートも、中国の書聖・王羲之も驚きだろう。 お陰で分量はページ数ではなく文字数で把握されるようにもなっている。 まさに千言万語の復活だ。 そう考えると、デジタル書籍の数え方も『冊』ではなく『巻』と読むべきかもしれない。 いや『巻』というのも何を巻いているの? という話になるから、やっぱり『作』がふさわしいか。 そういえば、同じ作品の続き物を2巻3巻と呼ぶのはなぜだろう。 それと漫画の単話タイトルで『○○の巻』と付けたのは誰だろう。 何も巻いていないのに、なぜ『巻』と呼んだのか、忍者ハットリくんが最初ではないと思うが。 [一日三報] [INTERNET Watch] オンライン会議で相手からの信頼を得たい場合に「背景に置くべきモノ」は? 英大学の調査で判明
これは何もオンライン会議の発展によって生まれたスタイルではなく、ごく一般的に会社やテレビ番組の演出として使われているものだと思う。 テレビに出てくる専門家や大学教授は、いつも背景に大きな本棚を置いている。 これだけ勉強しているからエライのだというイメージを与えるためだろう。 それよりも、ノートパソコンに搭載されたWEBカメラを使うと、どうしても下から見上げた「下ぶくれ画角」になってしまう問題をなんとかすべきだと思う。 [ITmedia] 巨大キートップを頭にかぶる「帽子型キーボード」、Googleが公開 キーボードの“ボー”に着目
今日の悪ふざけ。 こういうネタは積極的に取り上げてもらわないと寂しくなるから大変だなと思う。 「塩が足りない」ネタを投入したところで、割とおじさんが頑張っているのが分かる。 [読売新聞] 「ぽたぽた焼」パッケージ、現代的おばあちゃんに世代交代…ヨシタケシンスケさんが描く
どの辺りが現代的なのか分からないが。 和服に割烹着のおばあちゃんなんてコスプレだと思うが、スラックスにカーディガンのアクティブおばあちゃんもイメージではないのかもしれない。 チャイナ坊やが変なラッパーになったベビースターラーメンのように、もうちょっとはっちゃけても良かったと思う。 |
|
| |
||