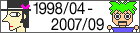|
|
||
| archive
|
[今日の独言(ひとこと)] 【誤表記『危い』が残り続ける理由】
文章のデジタル化により圧倒的に数を減らしたのは「送り仮名の付け間違い」だろう。
誤字や脱字はなくならないが、送り仮名の付け間違いは自動変換によってほぼ存在しなくなった。 「大きい」か「大い」か、「恭しい」か「恭い」か、「潔い」か「潔よい」か迷って困って辞書を引く人はもういない。 これは文章の校正もとても楽になったことだろう。 それでもたまに、おかしなことになるから危ないのだが。 「危い」という言葉がある。 いや、実際にはない。 「あぶない」は「危ない」で、「あやうい」は「危うい」だ。 「やばい」は平仮名だ。 しかし世間の看板や道路では「危い」という表示を見ることがある。 私は勝手に「あぶい」と読んでいる。 「危い」という表記が氾濫する理由は3つあると思う。 ひとつは、そのほうが分かりやすいから。 「危ない」場所や状況は緊急に知らせる必要がある。 人は「危い」と見れば瞬時に「危険だ」と認識できるので、余計な送り仮名を付けるよりは、その分文字を大きくした方が良いだろう。 もうひとつは、「ない」という言葉を避けたいから。 「ない」は「無い」に通じるため、「危ない」を「危険ではない」と判断される恐れがある。 普通はそんなことはないが、日本語に不慣れな外国人などの判断を迷わせる可能性もあるだろう。 最後のひとつは、「特に決まっていなかったから」。 実際「あぶない」の送り仮名が「危ない」であると正式に決まったのは、たった50年前の1973年のことで、それまでは曖昧なままだった。 同じように「大きい」「承る」「悔しい」「明るい」なども制定された。 それまでも慣例として適切な送り仮名が使われていたが、法律があったわけではなく、実際小説や雑誌などでは混在していた。 「危い」も決して間違いではなかったのだ。 ということで「危い」の誤表記は未だに残り続け、これからも新たに作られることだろう。 なぜならそれで損をする理由もないからだ。 小説などでも、本当に必死なシーンなら漢字や送り仮名をわざと間違えて緊迫感を出すのも面白いかもしれない。 編集者や校正者の理解が得られるならば。 「誤字でーす、送り仮名間違ってまーす」とか悠長に指摘している者は命を落とすのだ。 [一日三報] [FNN] 「タイパ」で節約した時間は有効に使えてる?効率性を求め時間を節約しないといけなくなった背景にある人々の変化
書籍の宣伝のようなので言及するものでもないと思うけど。 どうも周りを見る限り、「タイパ」とか「コスパ」とか言っている人って、いつも周りをキョロキョロ気にしているキョロちゃんか、それを煽って商売にしている人くらいに思える。 少し前に流行ったライフハックだの断捨離だのを言い換えただけのような気もしたり。 いずれにせよ、一番タイパとコスパが良いのはメディアを無視して何にも触れないことだと思うわけで。 禅寺への出家をおすすめしたい。 [産経新聞] LINEヤフー、情報流出の詳細公表 個人情報など44万件流出か クレカ情報は含まれず
20年前なら社長が会見を開くレベルの大失態だったのに、情報流出もヌルくなったと感じる。 結局、情報は流出するものであり、個人情報は保護されないものであるという認識が当たり前になってしまったからだろう。 とはいえ、行政と連携して手続きが行えたり、マイナンバーカードが認証できたりするのは信じられなかったけど。 サケの放流じゃないんだから。 [ITmedia] Windows 11にアップグレードできないPC、国内に2000万台 “10サポート終了時”でも1000万台近く残存か
だってもうアップグレードはしないって言ってたじゃん。 忘れてないよ。 [今日の独言(ひとこと)] 【周回遅れのコロナ観】
先週一週間、新型コロナウィルス感染症に罹患して倒れていた。
今さらコロナだ、この3年間、緊急事態だのパンデミックだのと脅され続ける中、まったく罹る気配もなかったのに。 ちなみについ3週間ほど前はインフルエンザで倒れていた。 私はもうすぐ死ぬんだなと思った。 コロナとインフルエンザを近々で罹患した私の感覚で言うと、やはりコロナはインフルエンザよりきつかった。 高熱が4日間続いて、これまで体験したことのない頭痛に襲われて、信じられないほどの喉の痛みに苦しめられた。 かの戦国武将、丹羽長秀は晩年、積聚(しゃくじゅ)というクチバシの尖った亀のような寄生虫(と言われている)に苦しめられたという。 そしてついには「この丹羽長秀、積虫(せきちゅう)ごときに殺されようか!」と激怒した上、腹に短刀を刺して死んだそうだ。 まさに豪傑、天晴れな死に様。 その気持ちが凄くよく分かった。 でも私は首を斬り落とす勇気がなかったので泣き続けて、なんとか回復した。 言えることは、コロナは弱毒化したというのは全くの嘘だ。 確かに私は死んでいないし、入院もしなかった。 しかし弱まっているとは決して感じなかった。 気軽に罹って切り抜けられる病気ではないはずだ。 ここへ来て思うのは、あの頃さかんに言われ徹底されてきた感染症対策は決して無意味ではなかったということだ。 手洗いやうがいやマスクやソーシャルディスタンスなどなど。 その効果は当時激減した季節性インフルエンザを見ても明らかだった。 みんなが協力すれば、あそこまで感染を抑えることができた。 それなのに、どうして止めてしまったのだろう。 新しい習慣、ニューノーマルだのと持て囃していたのに、なぜそれ以前の不潔で怠惰な日常に戻ってしまったのか。 「喉元過ぎれば熱さ忘れる」の心理というものか。 社会って本当に不思議なものだと思っている。 なお今私は、この頃ずっと解消しない倦怠感を抱えているが、それがコロナの後遺症なのか、元からそうだったのか思い出せないでいる。 だるい。 [一日三報] [INTERNET Watch] 「これだからサブスクは」安室奈美恵さんの楽曲配信、予告なく一斉停止でファンから悲鳴
ご存じの通りサブスクというのは商品を購入しているのではなく、商品を使用できる権利を購入している。 この場合は楽曲を聴く権利を得ているに過ぎず、つまりはいつ何時聴けなくなっても誰も文句は言えないのだ。(もちろん保証期間外) だから本来は製品版よりライトな位置づけで、所有するほどでもないという客向けに安価で提供すべきサービスなのだが、結局は保存版もサブスクに駆逐されていってしまった。 膨大な娯楽や情報が提供される時代になったが、気がつけば何一つ所有を許されない時代にもなりつつあると思う。 [朝日新聞] 西之島、新島誕生から10年 拡大する島、リセットされた生態系は今
今日の西之島。 これって多分、世界的にも物凄く貴重なサンプルなんだろうね。 死の島への最初の移住者が、鳥の他にはワモンGというのが興味深い。 その場所だけで生命活動を維持できることが生息の条件とするならば、人類がこの島で住めるのはまだまだ先になりそうだ。 [NHK] 「研究者カード」産総研が作成 最新科学技術をPR 茨城 つくば
オモテ面にキラキラの顔写真を載せて、ウラ面にプロフィールと作品名を紹介した「プロ作家カード」を作ってポテトチップスのオマケに付けたい。 という提案を以前したことあるが、誰一人として賛同は得られなかった。 もちろん私も嫌なので企画はお流れになった。 でもまあ名刺代わりには使えそうね。 [今日の独言(ひとこと)] 【AIは人に幸福をもたらすか】
英語辞典「コリンズ」を出版するハーパー・コリンズの英国法人は、今年よくに使われた単語「ワード・オブ・ザ・イヤー」に「人工知能(AI)」を選んだと発表した。
他にもネポティズム(縁故主義)とベイビーを合わせて、いわゆる「親ガチャ」を意味する「ネポベイビー」や、インフルエンサーが「買うべき」ではなく「買ってはいけない」を伝える「デ・インフルエンシング」なども候補に挙がっていた。 何はともあれAIのトレンドはまだまだ続いているらしく、猫も杓子もAI、AIと喧伝している昨今。 一昔前の「マイコン」のように、「うちの商品にはAI入ってますから!」も売り文句になりつつあるようだ。 先週には生成AIを使って総理大臣の口真似で下品なコピペを話すフェイク動画も話題になっていた。 少し前にはトランプ大統領も似たようなことをされていたが、せっかくみんな楽しい玩具で遊んでいるのに、空気の読めない馬鹿がそういう問題を起こして規制が囁かれるようになるのは残念だ。 AIはインターネットに次ぐ技術とも言われており、今後はますます発展が見込まれているらしい。 つまり今はまだなんのことが分からない人たちも、インターネットがそうであったように、やがて様々なツールに入り込んで、知らなくても使っている社会となっていくのだろう。 そして、かつて「IT革命」と騒がれていた時代と同じく、AIによって奪われる職種、業界の話も出ている。 いつも不思議に思うのだが、便利さを求めて生み出されたツールによって人間が路頭に迷うのはなぜだろう。 人の仕事を機械が肩代わりしてくれるなら、仕事をしなくても良くなり幸せになるべきだと思うのだが。 どうも政治や社会や人間がテクノロジーについていけていない気がしている。 [一日三報] [NHK] 十徳ナイフは違法・合法?わかれる司法判断
銃刀法では刃渡り6センチ以上の刃物を規制している。 ちなみに刃物でなく鈍器でも規制対象なので、理由なくハンマーやスパナを持ち歩いていても摘発される可能性はある。 とはいえ警察も面倒なのでいちいち捕まえたりはしない。 告発者が不運なだけかもしれないが、その前に警察とどういうやり取りがあったのか気になる。 [産経新聞] 全米に押し寄せる「万引の波」 凶悪化で閉業相次ぐ
「万引き」は「間引き」が由来で、畑で芽を間引くように陳列している商品を抜き取る行為を示している。 ということで、これは単なる略奪強盗だと思う。 社会の規律は何かのきっかけで崩壊することがある。 その分水嶺はどこにあるのか、日本でもひょっとしたら起こることかもしれない。 [AFP] 2.9億円の「醜い」噴水に批判殺到 ウィーン
美醜の判断はどこにあるのか。 制作者の「ジェラティン(Gelitin)」を検索してみたら、割と今までも似たような作品を製作しているようなので、問題があるとすれば彼らに製作を依頼した担当者とその賛同者にあると思う。 日本でも駅前にいきなり変な像が建てられたりするよね。 ああいうのも偉い人たちが、素晴らしい、これは良いとか言って決めているのかしら。 [今日の独言(ひとこと)] 【設置型コンテンツの未来は】
プロ野球の日本シリーズは、阪神タイガース対オリックスバファローズと59年ぶりの関西対決となった。
お陰で関西というか大阪は、連日マチやテレビで大いに盛り上がり、痩せても枯れても野球人気の健在ぶりをアピールしていた。 なんやかんや言うても、みんな好きなんやね。 私は野球には特に興味はないが、それでも過去に何度か球場に連れて行かれたことはある。 スポーツはテレビで観るものと実際に観戦するものとは全く別物で、ルールも選手も大して知らなくても興奮させてくれる。 雰囲気に呑まれるとでも言うのだろうか。 周りの人たちが笑顔で手を叩いていると、赤子も笑って手を叩くような、そんな社会性動物の琴線に触れるものがあるのだろう。 そんな風に、見ると行くとでは大違いのコンテンツとして、他にもサーカスがある。 アクロバットな演技やコミカルなパフォーマンスは映像で見ても同じはずだが、やはり実際に目の前でやられるとその臨場感に圧倒される。 空中ブランコだの、椅子を積んでその上で逆立ちするだの、ありふれたものでも感動させられる。 どう考えても今時は経営の厳しいエンタメビジネスだが、それでも廃れ切ってしまわないのは、そんな魅力に気付いているファンも多くいるからだろう。 ドイツのサーカス団「ロンカリ」では、今3Dホログラムを用いたライオンやゾウのパフォーマンスショーを行っているらしい。 動物保護の観点から1991年からライオンとゾウのショーを中止し、2018年からは全ての出し物に生き物を使わなくなった。 そして今では複数のカメラを用いて高解像度で動物のショー、もちろん強いられた演技ではないものを見せて観客を楽しませているそうだ。 サーカスの舞台の暗さと狭さを見れば、3Dホログラムとの親和性の高さは容易に想像できる。 実際に動物を飼育し運搬することを考えるとコスト的にも有効な手段だろう。 ネットとスマホの全盛期に設置型コンテンツで客を呼び込むのは難しいが、工夫次第でプレミアムな体験を提供できる。 というか、スポーツ観戦や映画、サーカスに至っても、これからは庶民の娯楽からセレブのアクティビティになっていくと感じている。 コンサートチケットが高騰化している話もこの頃はよく耳にしている。 貧乏人はスマホで観とけってことだろう。 いつでもどこでも同じクオリティで楽しめるのは小説くらいなものだね。 [一日三報] [まいどなニュース] 勉強できない子は漫画も読まない!? 受験の偏差値との比例説が賛否両論
令和の世とは思えない、昭和な議論。 まあ昭和の頃は「本も読まない子は……」って話だったが、今はその対象も漫画になっているわけで。 本質は漫画がどうという話ではなく、能動的に何かを得ようと考え行動するかという話ではないかと。 地べたに座ってヒマだヒマだと言ってる子は、頭が悪いからそうなっちゃうのだ。 [ITmedia] 「前歯を舌でタップ」「舌をかむ」 VRヘッドセットを“舌操作” 米Microsoftが開発
アップルウォッチのハンドジェスチャーもあるけど、なんだかそういうセンサーも発展しているっぽい。 でもVRヘッドセットを付けながら、舌打ちしたり口をモゴモゴさせている人ってなかなか怖いよね。 [CNN] 猫の表情は276種類、米の猫好き研究者が特定
ちょっと眉唾。 ただ言語によるコミュニケーションがない以上、動きや表情による効果は人間以上のものがあるような気もする。 無表情のまま、身じろぎひとつせずに、静かな怒りを伝えられるのは人間だけだ。 僕らももっと積極的にボデーランゲージを取り入れるべきかもしれない。 |
|
| |
||