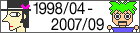|
|
||
| archive
|
[今日の独言(ひとこと)] 【人生の、残り○冊】
お陰様で今年も無事に誕生日を迎えて、またひとつ歳を重ねてしまった。
いつまでも若いつもりでいるが、実際は結構な歳だと自覚もしている。 気持ちはハタチのつもりだぜ、というセリフは、要するに何も成長していないと宣言しているようなものだから、控えるべきだと思っている。 計算すると、親の顔が見られるのはあと10日くらいかもしれない。 実家から遠く離れ、年に数回の帰省しかできない人はよくそんなことを言う。 同様に、一生の内で食事ができる回数は限られている、という言葉もある。 1日3食、1年で1095食、10年で10950食、ただし夕食に限れば3650食。 その貴重な一食をインスタント食品で済ませていいのか、という論法だ。 同じように考えると、実は今後読み終えられる書籍の冊数も決まっている。 時間には限りがあり、一年で読める本の冊数も大体決まっている。 それに自分が思う寿命をかければ、それがあなたの生涯で読める本の数だ。 本でなくとも映画でもいい、ゲームでもいい。 山登りでもいい、サーフィンでもいい。 貴重な一回を、そんな山でいいのか、そんな波でいいのか。 そうやって危機感を募らせて、高級布団などを買わせるお仕事もあります。 大阪のとあるビルには、「闘病記」だけを集めた図書館があるという。 出版社が運営しているもので、自費出版の案内なども行っているそうだ。 闘病記というのは当人の人生にとっては物凄いターニングポイントになるが、それ以外の人にとっては見向きもされないことが多い。 商売として見れば、ガンや認知症なら患者も多いので読む人もいるだろうが、その他の、聞いたこともないような名前の難病を扱った闘病記は誰の目にも留まらず売ることも難しいだろう。 しかしそれが、もしかすると、誰かの手助けになることもあるかもしれない。 そんな本の本質、出版することの意義を考えると、いい取り組みだと思った。 それはそうとして、ミステリーやホラー書籍専門の図書館や、SFや恋愛書籍専門の図書館があっても面白いかもしれない。 他のジャンルは何も扱っていない、ただしオカルトに関しては、古代シュメール文明から最新AIの陰謀まで、数多く取り揃えております、とか。 短い人生に読む貴重な一冊だ、流行にとらわれずに吟味できるサービスが欲しい。 今年もお世話になりました。 来年もまたお世話をよろしくお願いします。 [一日三報] [読売新聞] 闇バイト応募者に「受け子」適性テスト、試験官役の男「ロボットのように動くか見極め」
悪い奴は手下も悪い奴ばかりなので、寝首を掻かれることもある。 自分勝手で疑り深い上に、なけなしの倫理観なぞも抱えている私たちは、悪者の手下にすらなれないのだ。 [毎日新聞] 「SNSに載せる」「映画料金払え」 鉄道でのカスハラ1124件
特に日本の都市部において電車というのは、老いも若きも、お金持ちも貧乏人も利用する機会が出てくるもので、畢竟、色んな人のルツボになっている。 それがまた面白くもあり、難しくもあると思う。 理由は色々とあるだろうが、まあ、黙って耐え忍んでいても報われない社会になったというのも理由にある気がする。 でも昔は昔で、ひどい駅員さんも多かったよ。 [Gigazine] アメリカ人男性の半分は「自分なら旅客機を緊急着陸させることができる」と思っている、専門家の見解は?
トム・クルーズのせいか、ブルース・ウィリスのせいかは分からないが。 オレオレ詐欺なんて、うちにかかってきたら撃退するのにとか、教室に暴漢が来ても俺ならやっつけてやるのにとか、そういう男子の妄想に近いものがある。 心理学的にはどういう説明がなされるのだろう。 この「自分ならもっとうまくやれるのに」感は。 [今日の独言(ひとこと)] 【世界を動かすタイミング】
今年話題になったクリストファー・ノーラン監督の新作映画「オッペンハイマー」が、紆余曲折を経て2024年に日本でも公開されることになった。
第二次世界大戦中に原子爆弾を開発した「原爆の父」と知られる理論物理学者ロバート・オッペンハイマーの生涯を描いた伝記映画だ。 アメリカではすでに7月21日に公開されて大ヒットを記録したが、日本では極めて気に障るテーマなので公開はおろかほとんど話題にすらなっていない。 少なくとも夏に日米同時公開などできるはずがない。 この両国における「戦争の夏」に対する感情の違いは今後もずっと受け継がれていくだろう。 なお私自身は創作に禁忌なし、商売に貴賤なしが性分なので、作品にケチをつける気は全くなく、公開されたらそのうち目にしようと思っている。 キャストを見るとアインシュタイン役が「戦場のメリークリスマス」に出演したミスター・ローレンス(トム・コンティ)なのが面白かった。 生きとったんか。 先日にはファッションブランド「ZARA」が打ち出した広告キャンペーンに非難の声が上がり撤回される事態があったらしい。 瓦礫や壊れたマネキンが横たわる中でモデルがポーズを決めているイメージだったが、それが連日報道されているパレスチナ自治区ガザ地区の光景を想起させるという理由だった。 既存の概念や価値を破壊し、新たなものを生み出すというのは、ファッションに限らずポスターなどでよく使われるモチーフだが、タイミングが悪かったようだ。 中国では香港の有名シェフが11月27日にSNSに卵チャーハンの動画を投稿したところ大きな批判を浴び、シェフが2度と卵チャーハンをつくらないと宣言する事態にもなったらしい。 理由は動画を投稿した2日前の11月25日といえば、毛沢東の長男、毛岸英が1950年に戦場で卵チャーハンを作っていた際の煙が見つかり、米国の空爆により戦死した日だからという。 そのため氏の誕生日のある10月と戦死した11月は、卵チャーハンに対して国家主義者が非常に神経質になっているそうだ。 家紋がキュウリの断面に似ているから食べてはならない、みたいな話だと思った。 なお当のシェフは2018年にも2020年にも10月に卵チャーハンの動画を公開して謝罪しているらしい。 そうなると、ちょっと、どっちがどうか分からなくなってきたぞ。 何事も時代、時流、時勢、時節、時期に配慮する必要があるようで。 あなたが何気に投稿したオムライスの画像なども、誰かを傷つけたり、怒りを買ったりする可能性があるのだ。 知ったこっちゃないけどね。 [一日三報] [毎日新聞] H1グランプリに岡山の小谷さん
今日の奈良。 正式名称が「H1法話グランプリ2023」なのに「法話」を取った「H1グランプリ」を見出しに使ったのは、きっとスケベな男子を釣ってPVを上げる戦法なのだろう。 くそ期待させやがって。 それはそうと、お話がびっくりするくらい下手なお坊さんっているよね。 [PCWatch] 米中SSDの耐久対決、3カ月書き続けてついに決着。勝ったのは……
興味深いけど長い記事。 よく分からない人は最後の2段落だけ読めば事足ります。 こんな風に黙々と調べている人たちのお陰で、面倒臭がりな僕たちが助けられている面も大きいと思う。 何年分ものパーティの収支報告書とかを見続けている人もしかり。 感謝しましょう。 [今日の独言(ひとこと)] 【標識における法隆寺テンプル問題】
北海道の小樽市にある市道の道路標識に30年以上前から誤りがあったというニュースが先日報道された。
その道路標識には「札幌」「余市」「小樽港」のそれぞれに向かう道路が示されていたが、その内の小樽港の英語表記が「Otaru Port」とすべきところを「Otaru Poot」と誤表記されていた。 「Poot」は米国の俗語で「おなら」や「うんち」といった意味になる。 市の建設事業室は早急に修正するとコメントし、実際にもう修正されたようだ。 しかし30年以上もそのままであったなら誰も見ていないか、見ても気にしなかったのだろうから、別にそのままでも良かったんじゃないかと思った。 英語のスペル間違いは当然良くないことだが、実際それが緊急事態になるかというと、そうでもないことも多い。 英語圏の人も日本語圏の人と同じように文脈から単語を推測できるので、「Otaru Poot」を見ても「小樽港」ときちんと認識できたことだろう。 私はそれよりも「Otaru Port」という表記のほうが気になった。 「Otaruko Port」ではないのだろうかという疑問だった。 道路標識に「法隆寺テンプル」問題というのがあるのはご存じだろうか。 知るわけがない、私が今勝手に作った言葉だからだ。 これは「法隆寺」の「寺」は名称の一部なのか、それとも施設の形態なのかという問いだ。 つまり名称の一部なら「Horyuji-Temple」となるが、施設の形態なら「Horyu-Temple」となってしまう。 「Horyu-Temple」がおかしいと言うなら、先の小樽港も「Otaruko-Port」にすべきではないかという話だ。 以前、横浜に行った時に見つけたが、そこの標識で「中華街」は「China Town」と表記されていた。 一方で「赤レンガ倉庫」は「Aka-Renga Soko」と表記されていた。 とはいえ「China Town」で「中華街」と気づけても、例えば「Red Brick Warehouse」で「赤レンガ倉庫」と気づけないかも知れない。 道路標識のルールは厳密ではなく、それを道行く日本人に口頭で伝えた際に、日本人の英語力と想像力で意味が理解できるか、を重要視しているのだろう。 道に迷った外国人観光客には優しく接しましょう。 ちなみに私が今一番気になっている表記が「奈良文化財研究所」だ。  古都奈良の文化財の研究や遺跡の発掘調査を行う機関だが、2018年に立派な新庁舎が建てられた。 その際、施設の建物の右肩に「奈良文化財研究所」と切文字の名称を掲げたが、その下にはなぜか「NABUNKEN」と略称のローマ字表記が付いているのだ。 これは一体、どういう意図があるのだろう。 日本語の読める人は上の正式名称が読めるが、英語しか読めない人は意味の伝わらない謎の略語しか読めない。 それとも「なぶんけん」にそれほどの知名度があると思っているのだろうか。 もちろんWEBサイトの英語版では「Nara National Research Institute for Cultural Properties」と正式名称で表記されている。 一体誰のための、何のための「NABUNKEN」表記なのか。 目にするたびにいつも気になっている。 [一日三報] [読売新聞] 1000年続く「蘇民祭」、来年で最後に…JR東日本がポスター掲示断ったことも
インパクトのあるポスターで少し前に話題になった蘇民祭。 良くも悪くも、あれだけ注目されたのに廃れてしまうということは、もう仕方がないんじゃないかとも思う。 地域の伝統文化は続けて欲しい願いはあるが、自分がこのフンドシ野郎衆と肌を合わせてオラオラやるかというと、絶対嫌なわけで。 次の1000年に向けて新しい祭に取り組むのもいいと思う。 [ITmedia] 人気VTuberになりきり金銭を窃取、にじさんじ運営が注意喚起 声や話し方まねて本人と信じ込ませる
今時な詐欺。 物真似やそっくりさんの面白さは似ているところではなく、絶妙に似ていないところにあると思う。 中国の京劇に登場する関羽は、神となった将軍への礼儀として顔のメイクにホクロを付けて「本人ではない」と示すならいがあるとか。 次は人気VTuberになりきれていない、そっくりさんVTuberが流行るかもしれない。 [AFP] 高齢者狙いトコジラミ駆除詐欺、男2人逮捕 仏
今日のトコジラミ。 トコジラミ、南京虫と呼ばれているが、実はカメムシの仲間だ。 地球温暖化と飛行機旅行のプライスダウンと、アジア南部の富裕化による相乗効果で世界中に広まっている模様。 たぶん来年には日本でも大きな騒ぎになって流行語にも選ばれると思う。 [今日の独言(ひとこと)] 【図書館妖怪カタログ】
近くの図書館が新しくなったので行ってみた。
私が住む町の近くには郡部があって、そこには町立の図書館がある。 こじんまりとした建物に、中学校の図書室程度の蔵書しかないが、居心地が良いので機会があれば立ち寄っていた。 この度、その図書館が移転しリニューアルされたという。 それで一体どう変わったのかと気になり足を運んだ。 新しい図書館は同時に新設された役場の隣に併設されていた。 現代風にリビルドされた建物に入って驚いた。 何も変わっていなかったからだ。 広い建物を区切って狭いスペースを作り、そこに今までと同じ数だけの蔵書を並べていた。 もちろんカウンターやトイレは新しくなっていたが、だからどうした訳でもない。 やはり中学校の図書室程度に、古い本がみっちりと収まっていた。 結局のところ、利用者の人数と傾向を鑑みれば、この程度で十分という判断なのだろう。 役場や図書館が大きく綺麗にしても、人口が増えるわけではない。 それはそれで潔い判断だと感じた。 香川県の高松市中央図書館ではこの頃、所蔵する小説のページが破り取られる事件が頻発しているらしい。 作品の中には100ページ以上切り取られているものもあり、ミステリー作品の結末が読めなくなっているのもあるそうだ。 10年ほど前に東京各地の図書館で「アンネの日記」とその関連書籍の多くが破られる事件があった。 書籍の内容だけに思想犯か国際問題かと騒がれたが、結局逮捕されたのは精神科への通院歴がある30代の男性で、特定の思想に基づく行動とは認められないと判断された。 なんにせよ、市民のために広く開放されている公共施設は、それゆえにセキュリティも徹底し辛い面がある。 ただ近年はそういうこともあって、防犯カメラの設置や警備員の巡回を行う図書館も増えているようだ。 先の新設された図書館にも防犯カメラがあったかどうか、見るのを忘れていた。 図書館で起きるトラブルや、訪れるちょっと変てこな人たちを紹介した本があれば面白そうだ。 名付けて図書館妖怪(っぽい人たち)カタログ。 でも今日びの風潮では取り扱いが難しいかもしれない。 [一日三報] [Forbes] 年賀状「送らない」人が多数派に 10代は手描きが半数以上
私はもう数年前に「年賀状じまい」をして、これまで送っていた方々に「来年は送りませんから」宣言をした。 結果、何が変わったかというと、見事に何も変わらなかった。 親しい人とは別の方法で連絡が取れるし、途切れてしまった人もいるが、きっとお互いにスッキリしていることだろう。 とはいえ年賀状は未だに14億4000枚も発行されているらしい。 一枚63円となると、まあかなりの稼ぎ手ということで、いつか終わるその日まで少なくなっても続けられることだろう。 [読売新聞] ネットで提案されているクマ対策は有効か、専門家に聞いてみた
そんなもん聞くなよとも言いたくなるが、予想通りの全否定。 しかし問題の本質はクマの保護ではなく、キュートなクマちゃんをいじめないでという人たちや、なぜか人類の罪を背負いたい人たちの思いにあるので、結局何を語っても伝わらないと思う。 家のゴキブリや庭の雑草は駆除するくせにねぇ。 [日本海新聞] コナン君が一緒に旅へ スーパーはくと ラッピング列車始動
できれば一緒に旅をしたくない人ナンバーワンを扱う命知らず。 それならいっそ車内でフェイク殺人事件を起こして盛り上がるというのもアリかも。 まあ最終的にはなんかボールを蹴って解決するんだけど。 |
|
| |
||